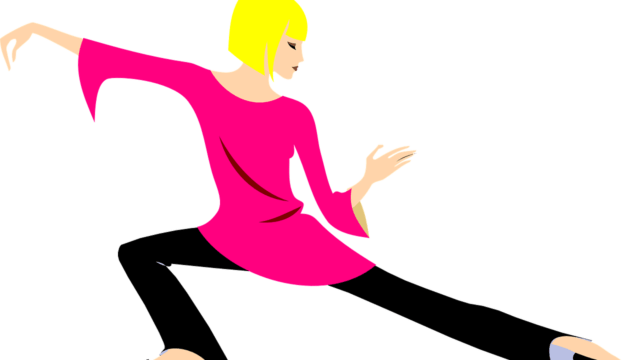Contents
『ギックリ腰は尻から治す 激痛を最短で治し、再発を防ぐ腰痛改善メソッド』伊藤和磨著 永岡書店

ギックリ腰を体験した人はあの突然襲ってくるいや~な感覚を忘れられないと思います。
かくいう私も、忘れもしませんが高校1年生のときに突然のギックリ腰を体験して校舎の階段をはって歩いた思い出があります。
その時はいったい何が起こったのかよくわからず、とにかく幽霊をみたような態で階段を両手をつかってなんとか這い上がったのをおぼえています。
それから長い腰痛人生が始まりました。その長い腰痛人生のなかで、腰痛に関する本を読みまくってきた中で今回取り上げるのは『ギックリ腰は尻から治す 激痛を最短で治し、再発を防ぐ腰痛改善メソッド』です。
この本は元Jリーガで選手時代にひどい腰痛を患って引退を余儀なくされた経験もある現在はパーソナルトレーナーをされている伊藤和磨さんです。
自分自身のご経験から数々の腰痛に関する本を出版されています。この本『ギックリ腰は尻から治す』はその中の1冊です。
伊藤さんの著書はほとんどすべて読んでいるのですが、個人的に勝手に親近感を持っています。
というのも原因不明の腰痛に悩まされて病院にいっても治らず、通り一遍の対処療法や患部へのブロック注射も痛いだけで腰痛自体は治らなかったという経験は伊藤さんと共通のものだったからです。
いわゆる外科治療で原因が特定できる腰痛の疾患は、椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症のふたつです。
原因が特定できるというのはレントゲンやMRIをとった場合に患部が画像で認識できるということです。
しかしこのような疾患の腰痛に占める割合はわずかに2割程度で、圧倒的多数の腰痛はレントゲンに映らないので原因不明とされてしまうのです。
しかしレントゲンには映らなくとも原因がわかっている腰痛はたくさんあります。今回はこのような腰痛について、その発生メカニズムと対処法について紹介したいと思います。
ギックリ腰は誰にでも起こる

本にも書かれている通り、欧州の人々はギックリ腰を「魔女の一撃」といって忌み嫌って怖れてきました。
ただこの魔女の一撃はいきなり襲ってくるように見えて、実は予兆があります。
残念ながら僕自身は何分高校時代のことなので突然という印象しか残っていないのですが、伊藤さんは何度もやってるために、その予兆を感じ取れるようになったといいます。
そこで伊藤さんが挙げられている5つの予兆を危険度を1から5段階で表して紹介します。
- ふくらはぎがパンパンにはる
- お尻の頬っぺたに強いハリ感がある
- 骨盤の中心(仙骨)に強張りを感じる
- 骨盤が片側にスライドしている
- 立ち上がる瞬間にビリっとした痛みを感じる
身体の皮膚と筋膜はウェットスーツのようにつながって全身を覆っています。このつながりによって身体の一部に生じた力をうまく全身につたえることができるのです。
この身体のつながりのことを「キネティックチェーン」と呼びます。
キネティックとは英語で”kinetic”とかき、「運動学上」のという意味になります。
このキネティックチェーンのメカニズムにより、ふくらはぎで生じたこわばりはほかの部分にも伝染していきます。
この場合、太ももの裏側からお尻、仙骨へと伝わって、腰痛を発生させます。
ギックリ腰をよく起こす人は大体10日ほど前から、このふくらはぎのこわばりを経験するといいます。
次にお尻の筋肉にハリを感じたならそれは危険度2になります。
お尻の外側には腸脛靭帯と呼ばれるじん帯があり、これが膝関節と股関節をつないでいるのですが、この部分にハリが出て硬くなると、ひざや股関節の可動性を悪くしてそれが腰痛に結び付くのです。
次は危険度3の骨盤の中心にこわばりを感じるです。
骨盤の中心には仙骨と呼ばれる上半身と下半身をつなぐ重要な骨があります。
この仙骨を挟み込むようにして寛骨(かんこつ)があり、この仙骨と寛骨をつなぐ仙腸関節と呼ばれる関節に問題を抱えると、ギックリ腰が発生しやすくなります。
この仙腸関節ですが、お医者さんの間で椎間板ヘルニアが腰痛の元といわれる前までは、腰痛の原因は仙腸関節にあるというのが常識でした。
最近は再び仙腸関節由来の腰痛に注目が集まっています。
仙腸関節を支えるじん帯には様々な近くセンサーが走っていて、腰が丸まっている状態で長時間座っているとそのじん帯にストレスがかかって、それがセンサーを通じて広範囲に痛みの症状を引き起こすのです。
なのでこの場合は仙腸関節周りの部分をストレッチしてあげましょう。
その他テニスボールなどを地面においてそこに仰向けになってその部分にボールを当てて30秒ほど圧迫して、血流をよくしてあげることが有効になってきます。
危険度4は骨盤が片一方にスライドしているですが、これはつまりは上半身と下半身の中心軸がずれているということになります。
これは日頃の生活習慣で、いつも同じ肩に荷物をかけているとか、信号待ちしているときに利き足とは逆の足に体重をかけているとか、歯磨きをいつも利き手でしているとか、そういうことが積み重なって左右と上下のバランスが偏ってしまうことで起こるのです。
ですので普段から習慣になっている行動を見直して、普段とは逆の側を積極的に使ってあげる必要があります。
最後に危険度5のビリっとした痛みを感じるですが、これは真正のギックリ腰とは言わないまでもそれに近い非常に危険な状態です。
この警告を無視してそのままの行動習慣に従っていると、今度は真正のギックリ腰に襲われかねません。
このビリっとした痛みは腰椎付近にある多裂筋が緊張して固縮していると起きやすいといわれています。
なので先ほどのテニスボールより小さめのゴルフボールなどを使って同様に圧迫してあげてください。
腰回りのストレッチとともに、腰に負担がかかりにくい行動を心がけましょう。
下半身を置き去りにして上半身だけで物をとったり屈んだり、次の行動を予測しないでいきなり体を動かしたりすると、腰には大きなストレスがかかります。
そういうことがないように心がける必要があります。
腰に”スイッチ”をいれる
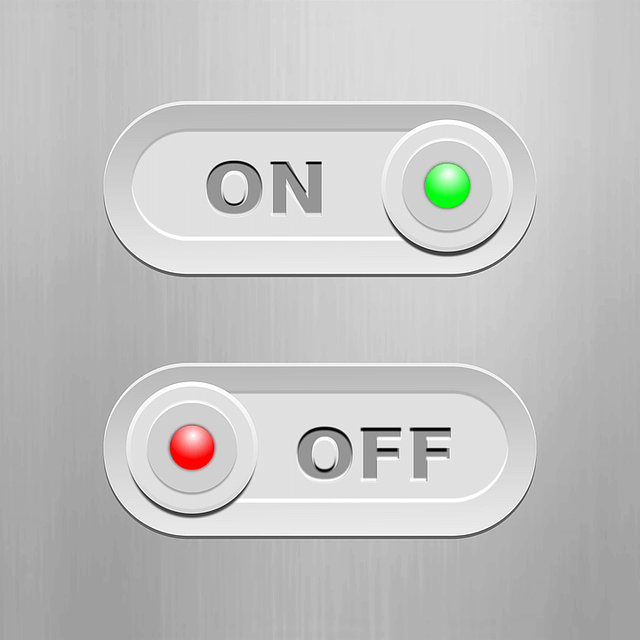
伊藤さん独特の面白い表現に、腰にスイッチをいれるという言葉があります。
腰にはスイッチがついていて、それを意識的にオンとオフに切り替えることで、ギックリ腰になりにくい腰に負担の少ない姿勢になるといいます。
私が腰痛を克服できたのは、腰に「スイッチ」があることを知ったからです。(略)どのような動きでも対応できるように、腰のスイッチをONにして骨盤を前傾させ、腰にそりを作っておけば、ギックリ腰の発症リスクをほぼゼロに近づけることができるのです。
もう少し詳しく腰のオンとオフについて解説してみます。
伊藤さんによれば腰がオフになっている状態は、いわゆる猫背になっていて骨盤が後傾している、つまり腰が丸まっている状態をいいます。
このとき多くの場合あごがでてしまっています。
これに対して腰がオンになっている状態とは、骨盤が前傾して、腰に緩やかな反りがある状態です。この時あごはひいています。
腰がオンになっていると腰椎と骨盤が連結して上半身と下半身が一体となっている状態なので、ギックリ腰になるリスクを最小化できるのです。
いわゆる良い姿勢というのは長い時間続けることはできません。
良い姿勢というのは自律神経の働きにより維持できるので、時々オンとオフを切り替えてやらないと疲れてしまいます。
なので意識的にオンとオフの切り替えをはかりましょう。
悪い姿勢ならなおさらという意味ですが、たとえ良い姿勢であってもずっと座っているというのも身体によくない行為なのです。
そもそも長い時間座り続けるということ自体が体の構造上不自然なので、たとえどんなに姿勢が良くても、体に負担がかかっていることはまちがいありません。
だるい、疲れやすいと感じる原因は年齢とともに衰える筋肉量でも書きましたが、本来は20~30分程度で一度席を離れるのが健康にとって良いことなのです。
ギックリ腰を起こす典型的な習慣は猫背
伊藤さんはギックリ腰を起こしてしまうのは日頃の習慣が大きく関係しているといいます。これを伊藤さんは腰痛習慣と呼んでいます。
同様にいくつか挙げられていますが、ここではその中の代表的な一つの習慣を挙げておきます。
それは腰がオフになっている典型的な状態である猫背です。特に座位での猫背姿勢が問題になります。
そもそもなぜ猫背になってしまいがちなのかといえば、骨盤の構造にあります。
人間は座位のとき横から見ると骨盤は二等辺三角形になっていて、座面に接しているのは坐骨であるために、骨盤はどうしても後傾してしまうのです。
では一体どうやって座ればよいのでしょうか。伊藤さんはいいます。
“椅子に座る”のではなく、脚を30度以上開いて”椅子に跨(またが)る”という意識を持つことが重要です。そして、座面と背もたれの角にお尻を差し込むようにして座ることが大事です。
キーワードは椅子に脚を開いて跨るように座るです。
この座り方をするとどういう座り方になるのかというとわかりやすくいえば?武田信玄のような座り方になります。
甲府駅前に武田信玄像が中座していますが、まさにあのような座り方が理想なのです。
椅子に跨るように座るといっても感覚的につかみにくいかもしれません。特に今まで悪い姿勢で座ってきた人にとっては言葉で言われれもつかみにくいかと思います。
そこで実際に馬にまたがっているような、鞍の上に乗っているような感覚で座れる椅子があります。
それが伊藤さんもお勧めしているサドルチェアと呼ばれるものです。
座位時の姿勢改善にサドルチェア

サドルチェアというのはまるで乗馬しているような感覚で座れる椅子のことです。
乗馬をされた経験のある人は少ないでしょうが、乗馬している人の姿勢を見ると背筋がすっと伸びて美しく見えます。
馬という生き物の背中に乗るわけですから元々安定感などないわけですが、下半身は脚を開いて鐙に乗せることで土台の安定感を作り、上半身は背筋を伸ばして前を向くことで、振り落とされないしっかりとした態勢を作れているわけです。
サドルチェアはそれを椅子で再現しようとするものです。
サドルチェアの特徴はなんといってもその形状が独特なことです。鞍そのものの形状をしているために一見どう座ろうかと考えてしまうぐらいです。
まさに座ろうというより跨るといった感じが正確でしょう。
通常の椅子ならお尻を座面に向けて降ろすといった感じで座ると思いますが、サドルチェアは横から足をあげて椅子をまたぐといった感じで跨ります。
サドルチェアといっても色々な種類がありますのが、僕自身が持っているタイプは右と左で座面が分かれている比較的安価なタイプです。
人間の身体は毎日の行動習慣の中で左右で偏りが生じてきますので、座面が水平で一つしかない場合だと、座っているとその偏りから無理が生じてきます。
しかしこのサドルチェアは左右別々なので、身体の偏りが左右で違っても左右別々に負荷がかかるので、上半身でうまく重心がとれて骨盤の偏りが是正されます。
そして左右に分かれていることで足を広げて座らざるをえないため、自然と開脚します。これが安定感につながり、上半身がスッと伸びます。
サドルチェアには背もたれがないため、代わりに座面の前部が湾曲してあげることでずり落ちずにバランスがとれるようになっています。
このため骨盤を前傾させても前のせりあげりによってせき止められるような形でストップがかかりますので、自然と骨盤が前傾した姿勢をとれるようになります。
この二つに座面が分かれていることのもう一つの効能は、男性に対してのみですが、骨盤を前傾させても局部に圧迫感を感じずにすむということです。
姿勢矯正用の椅子とのつきあい方
サドルチェア以外にも姿勢矯正のための椅子はいくつも開発されていますが、どれを選んでいいのかはなかなか判断が難しいところです。
というのも椅子の良さ、特に姿勢矯正用の特殊なタイプの椅子はそれなりに長い間使用してみないと本当のところ自分に合っているかどうかわからないからです。
ただ姿勢矯正の椅子には共通した特徴があります。
それは姿勢が悪かった人ほど姿勢矯正の椅子は最初のほうは合わないなと感じることです。
当たり前に聞こえるかもしれませんが、姿勢矯正の椅子へのレビューを読むと、結構このポイントが忘れられているなと感じます。
感覚的に合わない、座りにくい、良い姿勢が続かない、からダメな椅子であるという評価が多く見受けられるように感じます。
このようなレビューが多いのは、どこかで姿勢矯正の椅子に座り心地の良さを求めているからだと思います。
しかし姿勢矯正の椅子の目的はあくまでも姿勢を矯正することなのです。
姿勢矯正の椅子の評価は、姿勢が悪かった人が矯正されてどのくらい姿勢がよくなったかで本来計られるべきものですよね。
姿勢矯正の椅子に座っていると最初のうちはすぐに耐えきれないしびれを感じて席を立たなくてはいけなくなります。
これは普段使っていない筋肉を使わざるを得ないからです。
そうするとこの椅子は自分には合わないと考えてしまいます。
しかしこれはもったいないことです。
姿勢矯正用椅子は椅子というよりも、ある意味筋トレ用マシーンの一種と考えたほうが良いと思います。
みなさんジムにいってマシンでトレーニングするときに座り心地でマシンの評価を決めませんよね。
マシンの評価は狙った筋肉が効率的につくかどうかで決められるように、姿勢矯正用の椅子は姿勢がよくなるかどうかで判断されるべきものです。
おそらく最初のころは10分も座っていると苦しくなってくると思います。
そこでお勧めしたいのは椅子を矯正用と通常用の2つを用意するということです。
普段猫背の人が姿勢を良くしようとしても、最初は良い姿勢の感覚がつかみにくいために本人はよくしているつもりでも実際は骨盤がたっていないケースがあります。
そういう時に矯正用の椅子に座ることで骨盤を立てる感覚をつかみ、しばらく座ってみて限界を感じたら通常の椅子にもどるということを繰り返していると、そのうち通常用の椅子でもよい姿勢を維持していくことができるようになります。
最初から姿勢矯正用の椅子だけですと、座れなくなった時にもういいやとなって二度と座らなくなってしまうこともありえます。
なので椅子を2席用意しながら交互に座ることから始めてみましょう。
交互に座ることで、通常の椅子でも矯正椅子に座ったときの感覚で座ることになるので、その分早く通常の椅子でも良い姿勢で座る感覚を身に着けることができるようになります。
姿勢矯正用の椅子は体質改善が進んでいるかどうかのリトマス試験紙
姿勢矯正用の椅子は骨盤を立てて座る感覚を身に着けるのにとてもよい椅子ですが、この椅子にただ座っていれば姿勢が良くなっていくかというとそうではありません。
良い姿勢を維持するには今まで使っていなかった部分の筋肉を強化する必要があります。
猫背では背中が丸まって伸びていますが、良い姿勢では逆に背中は縮めてお腹と胸は張り出すように広がります。
なので良い姿勢を維持しようと思ったらその部分の筋肉の固縮を解消して強化する必要があるのです。
日頃から腹筋と背筋の筋力トレーニングとともにその部分のストレッチもやってあげることで、矯正用の椅子に座ってもよい姿勢をより長い時間維持し続けていけるようになります。
もし矯正用椅子に座ってすぐにきついと感じたならそれは良い姿勢を維持するための筋力が足りないということのシグナルであって、その椅子が自分に合ってないと考えるのは早計なのです。
ギックリ腰を治すストレッチ
慢性腰痛のひとつである坐骨神経痛に悩まされている人に効果的なストレッチの一つを紹介しておきます。
それが伊藤さんもお勧めする梨状筋へのストレッチです。
坐骨神経痛は仙骨からでている神経の束が、同じく仙骨の脇から付着して伸びている梨状筋が硬化短縮されることで圧迫されて起こることがほとんどです。
このため圧迫を無くするには梨状筋を緩めて伸ばしてやる必要があります。
言葉で説明するより動画を見ていただいたほうがわかりやすいので、下の動画を紹介しておきます。
これは寝たままでやるストレッチですが、座ったままでもやれるストレッチもあります。それが下の動画です。
次回紹介する背骨コンディショニングの日野先生が紹介するストレッチ坐骨神経痛に手術はいらないとあわせてやってほしいと思います。
最初に言いましたが、身体の皮膚と筋膜はウェットスーツのようにつながって全身を覆っているキネティックチェーンとなっています。
なので身体のある部分の痛みの原因が、そこから遠く離れた場所の固縮から始まっているということは往々にしてあることなのです。
したがって腰痛を抱えている人は腰痛に直接効くストレッチを頑張るだけではなく、できれば全身満遍なくストレッチをすることを習慣にできるようにがんばってほしいと思います。
ここで紹介している2冊目の本は同じく伊藤さんの著書なのですが、1冊目が主に文章で解説してくれているのに対して、2冊目の本は中村知史さんのすばらしいイラストで誰にもわかりやすい形で描かれていますのでこちらもお勧めします。