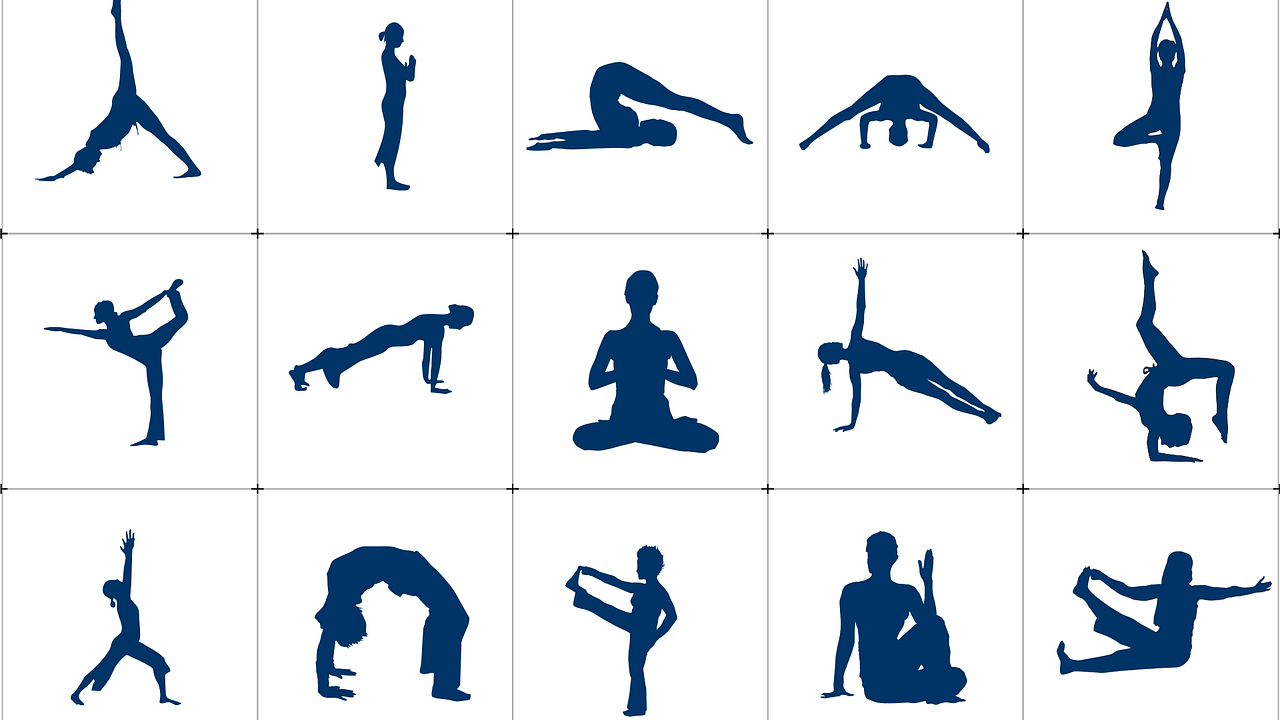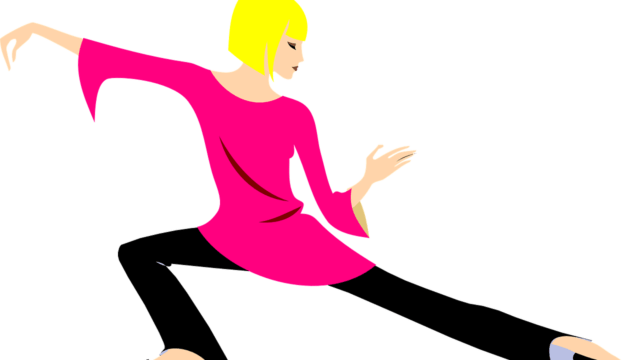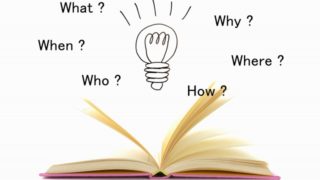『体が硬い人のためのヨガ』水野健二著 PHP研究所

ヨガというと、インドで生まれた瞑想を伴った体操術です。
この本『体が硬い人のためのヨガ Basic Lesson』の著者、水野健二さんは水野ヨガ学院代表でもあるヨガのトレーナーです。
ヨガというと、身体の硬い人には難しいと敬遠されがちですが、水野先生によればむしろ身体が硬い人ほどヨガを続けられているといいます。
というのも元々体の柔らかい人は、ヨガを習い始めてもすんなりとポーズができてしまうために張り合いが出ないからです。
実際、体の柔らかさを生かしてヨガ指導を始める人は多くいますが、そういう人は、私のまわりではいつの間にかヨガの世界から去っていきました。
体が柔らかい人は、ポージングは上手でも、硬い人への指導法がわからないのです。
しかしヨガの本当の面白さは、心と体が通じ合う点にあるといいます。
水野先生は、硬い体で良かったといいます。
というのも、硬い体だからこそ、体のうまい動かし方や感じ方を学べたからだといいます。
私にとってヨガのポーズを作る時間は、探しものをする時間です。
色々なことを考えながら、自分の硬い体で試してみる。そういう体験が、水野先生のヨガ指導に生かされているといいます。
自分も身体が硬い人間なので、水野さんが語る言葉にいちいち納得します。
自分のはヨガというよりもストレッチですが、体が硬い人間にとって初歩的なポージングでも十分に”効く”ポーズなので、やりがいがあるし飽きることもないのです。
もちろん、ヨガの曲芸師のようなポージングにあこがれることもありますが、それができることと健康であることとはまた別の問題です。
あそこまでできなくても、体の硬い人は初歩的なポーズで十分に体調を整えることが可能なのです。
その意味では、体が硬い人は、ほんの少しのヨガで楽しめる分得なのです。
ヨガにおけるイメージングの大切さ

ヨガを始めてやられる方はとにかく動けばいいだろうと考えがちですが、自分の身体の重さや感覚を大切にしながら動いてほしいといいます。
優しく丁寧に動くことで、体はそれに答えてくれるといいます。
また動作前のイメージトレも大事です。
そうすることで筋肉の緊張や疲労を伴わずに、筋肉をスムーズに動かせる神経回路をつくるのです。
イメージの力は自分が思っている以上に大きいものです。
たとえば、両手を合わせてそれぞれの中指の長さを比較してください。たぶんどちらかがわずかに長くなっていると思います。
短いほうの指にフーツと息を吹きかけて、長くなれと心の中で唱えてください。そして再び手を合わせてみると、あら不思議・・・。
開脚前屈のときでも、股のところが痛くてちぎれそうになる感覚がありますが、思い切ってちぎってみてはどうかといいます。
ちぎれそうということはちぎれないように身構えてしまっているということですから、もう少し緩められるところでも無意識にセーブがかかってしまっているのです。
なので、その「ちぎりたくない」という感覚を捨てて、ブチっといくイメージで緩めてみると、意外と緩むものです。
先生は、ヨガの様々なポーズはあくまでも目安であって、最初からそのまま完璧に真似る必要はないといいます。
ヨガのポーズで単純に形だけをまねて動いているうちは、体の感受性はなかなか磨かれません。
外側だけ真似をするのではなく、とんでもないポージングになっていてもよいから、自分が粘土細工になったつもりで、あっちこっちと体を動かしてみることが大切だといいます。
そうしているうちにいつの間にかポージングも様になってくるといいます。
大事なことは、骨と呼吸を感じながら、体の内側から緩めたり伸ばしたりする意識です。
水野先生によれば、身体で締めていても良い場所は、肛門と下腹部(丹田)と喉だけだといいます。
この動作前のイメージングというのは、ヨガやピラティスやストレッチだけではなく、筋力トレーニングの場合も大事です。
筋トレで大事なのは筋肥大させたい筋肉だけにいかに負荷をかけるかということですから、当該筋肉のストレッチと収縮を事前にイメージトレすることは、効果的なワークアウトをするために特に初心者は大切になってきます。
イメトレをしないままいきなり重い重りをもって負荷をかけると、筋肉や関節がびっくりして故障につながるリスクも上がってしまいます。
ヨガの呼吸法
ピラティスの記事でも呼吸法を紹介しましたが、ヨガとピラティスでは呼吸法が違います。
ピラティスが胸式呼吸なのに対して、ヨガは腹式呼吸です。
水野先生によれば良い呼吸とは、深くてゆったりとして強い呼吸のことです。
良い呼吸は身体をリラックスさせてくれるので、自然と肩がさがり、腹には力が満ちて、気持ちが楽になります。
これに対して悪い呼吸とは、浅くて速くて弱い呼吸になります。
水野先生が理想とする姿勢は、柔道や剣道などでも理想とされる「上虚下実(じょうきょかじつ)」と呼ばれる姿勢です。
上半身の力が抜けてリラックスして、下半身はどっしりと安定している状態を言います。
ヨガでこの上虚下実を体現している体位はやはり立位のポーズになります。立位とは立っているときのポーズになりますが、先生が薦められているのは英雄のポーズになります。
このポーズでもやはり肛門をしめることで、一気に姿勢が安定するといいます。
水野先生によれば、ヨガの呼吸は大きく分けて二つあるといいます。
それは普段の自然な呼吸と、集中するときの呼吸の二つです。
自然な呼吸とは、海や山など気持ちのいい場所にいって、身体を伸ばしたくなる時がありますよね。
あのときに身体を伸ばして空気を吸うような呼吸が自然な呼吸になります。なので自然な呼吸では、吐くよりも吸うほうが主体となる呼吸法になります。
これに対して針の穴に糸を通すようなときに行う呼吸が、集中するときの呼吸になります。このとき吐くほうが吸うときよりも主体となる呼吸になります。ここぞというときには、息を止めてグッと力を入れますよね。
自然な呼吸では身体や筋肉は柔らかくなりますし、集中するときは筋肉をしっかりと動かすようになります。
ヨガの同じポーズでも、呼吸の違いでその効果は変わってきますので、意識的に変えてみましょう。
ヨガにおける瞑想の意味
ヨガというと瞑想というイメージがありますよね。
ヨガのポージングというのは、先生もおっしゃるように、元々長時間座り続けながら瞑想をするために開発されたものです。
なので瞑想ありきなんですね。
ヨガから瞑想という軸をとってしまうと、極端な話ストレッチと変わらなくなってしまうと思います。
よく比較されるピラティスがどちらかといえば体の機能的な動きを追求するのに対して、ヨガは心と体のバランスを重視します。
水野先生も心と体のバランスが大事だといいます。
心と体はお互いにバランスをとって働くものなので、心のあり方をよくすることで体のあり方もあわせて改善されます。そして心を整えるためには、瞑想は素晴らしい訓練法です。
ヨガはスポーツではないし、他人と競争するものでもなく、あくまでも自分の心と体とが対話するためにあります。
そのためには、まず目的意識を捨て去ることが大事だといいます。
目的意識とは、例えばヨガをやることによってやせたいだとか、ひとよりも柔らかい体になりたいだとかですね。
これらはヨガを始めるモチベーションになりますが、やっている最中は頭の中からそのことを消し去る必要があります。
そのような雑念が入っていると、体と心の対話を感じ取るセンサーにバイアスがかかり、曲がるものも曲がらなくなってしまいます。
先生は、”あるがまま”とのを感じ取ることが大事だといいます。
あるがままとは日常で義務感でがんじがらめになっている意識を忘れて、大きな力や可能性を持った潜在意識をイメージすることだといいます。
そしてそれが瞑想です。
瞑想を一言で説明するならば「ものごとにとらわれやすい意識を小さくしていく訓練であり、具体的には「自由に動くことや、考えごとをするのをやめる時間」です。
先生が指導する瞑想のやり方は以下のようなものです。
- 坐骨の下に高めの座布団を敷いて、あぐらをかき、背筋を伸ばします。
- 舌の先を前歯の後ろにつけて、顔は力を抜いてやさしくします。
- 5分間を目標に、深くゆっくりと呼吸して、今とここしか考えないようにします。
座布団を敷くのは、初心者にはこのほうが姿勢が伸びて座りやすいからです。
座りやすいと瞑想に集中できますので、あとは雑念を捨てて、今とココしか考えないことにします。
瞑想が終わるとなんだか体が軽くなったような気して、リラックスできて体調も良くなります。
時間帯は朝にやるとその日一日スッキリとして過ごせますし、夜にやると頭の中身が空っぽになったような気がしてスムーズに就寝できます。
瞑想をしないでいると、その日ちょっとしたことでイライラしてしまう自分をみつけてしまいます。
もし最近怒りっぽいなと感じているのなら、生活に瞑想を取り入れるのは良いアイデアだと思います。
この本は、体が硬くてヨガを始めてみたいけれど、スタジオに行ってみる勇気はまだないという方におすすめだと思います。
つまり僕ですね笑。
ヨガの初心者が陥りがちな考え方をやさしく指摘してくれていますし、ポージングの心得についてツボを心得て教えてくれます。
またヨガの基本的なポージングをいくつも、桂早眞花さんによるすてきなイラストで説明してくれていますので、本当にわかりやすいです。
個人的には隠れた名著ではないかと思っています。また水野先生による最新刊もだされていますので、そちらも紹介しておきます。