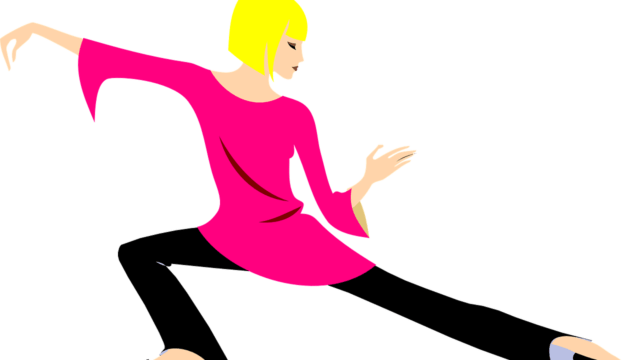『「体幹力」チューブトレーニング』木場克己著 新星出版社

チューブトレーニングというと、その名の通り、ゴムのチューブもしくはバンドを使ったトレーニング法です。
エクササイズを趣味としている人には、体幹のトレーニングというイメージがあると思います。
それは正しい認識なのですが、チューブトレーニングはそれだけではありません。
もともとチューブトレーニングはリハビリのために導入されました。
アスリートは肉離れなど、筋肉系の故障を抱えることが多く、そこからのリハビリには適切な負荷をかけながら、回復を計らなければなりません。
チューブならば、筋肉や関節に自重負荷をかけながら、細かい調整が可能になるのです。
スポーツができる前の段階で、ゆっくりゆっくり患部周りの筋肉を伸ばしていく。それができるのはチューブしかありません。
それでは、チューブはリハビリのためだけに使われているかというと、そうではありません。
多くのアスリートや、プロ選手、ハイアマチュアの方が、チューブトレーニングを愛用しているのです。
この本『「体幹力」チューブトレーニング』の著者、木場克己(こばかつみ)さんは、主に体幹トレーニングに関する著書をたくさん書かれているトレーナーです。
元々FC東京のトレーナーとしても活躍されていましたので、サッカー選手の体幹トレーニングにも詳しい方です。
木場さんも、チューブの効用をリハビリだけではないといいます。
体にぶれない軸をつくる
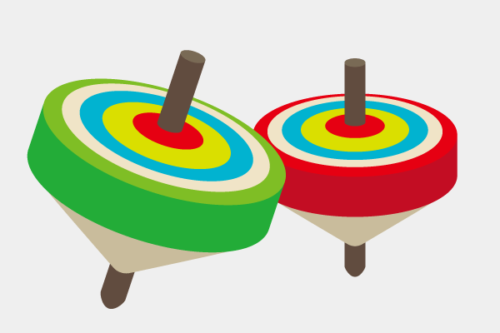
チューブトレーニングは体幹トレーニングの一種です。
身体には外側の大きな筋肉であるアウターマッスルと、内側深層部にあるインナーマッスルに分けられます。
インナーを鍛えることで、関節周りの筋肉に刺激が入ると、血流が増えて筋肉に柔軟性が生まれ、関節の可動域も広がります。
野球選手なら、肩甲骨周りの可動域が上がると投球動作の精度が上がり、サッカー選手なら、股関節周りの可動域が上がるとキックの精度が上がります。
またここら辺の関節と筋肉の柔軟性が上がると、ケガをしにくくなります。
大きな筋肉ばかり使っていると、そこにだけ負担がかかり、肉離れなどの故障をしやすくなります。
しかしその周辺や深層部のインナーを鍛えて使ってあげると、負担が軽減されて、ケガをしにくくなるのです。
サッカー選手なら、ボールを蹴るときに使う筋肉であるお尻から太ももにかけての大きな筋肉は大腿四頭筋や大臀筋、ハムストリングです。
これらの筋肉を鍛えると、キック力があがってボールを遠くまで飛ばすことができるようになります。
しかしここだけを鍛え上げても、身体の外側の大きな筋肉に振り回されて、身体の軸がぶれやすくなり、結局のところキックの精度は上がりません。
その周辺のインナーである中臀筋や内転筋、腓腹筋などをチューブトレでバランスよく鍛えてあげることで、大きな筋肉を振り回しても軸がぶれにくくなり、キックの精度も上がるし、故障もしにくくなります。
サンフレッチェ広島ユースを例に挙げると、毎年必ず10人前後いたケガ人が、体幹チューブを取り入れてからは1~2人に減ったという。
また、インナーをチューブトレで鍛えてあげることで、持久力を上げることもできます。
アウターの大きな筋肉は、短時間での爆発的な力を発揮するのに向いていますが、それだけではサッカーなどの持久力も要求されるスポーツでは、試合終了まで走り切ることはできません。
インナーはアウターほどの爆発力はありませんが、長い時間継続して稼働する持久力を持っています。
インナーを鍛えることで、試合の多くの時間をインナーがアウターの負担を軽減させてくれるので、ここぞというときのアウターの爆発力が期待できるのです。
筋肉だけじゃなく、神経系の回復も促す
チューブを使って筋肉を伸び縮みさせていると、筋肉だけを鍛えていると思われがちですが、それだけではありません。
チューブは関節を動かす神経回路の成長を促すのです。
関節には、動きを感知するセンサーのような機能を持つ固有受容器というものがあり、そこに刺激が入ると、脳に情報が送られ、脳はそれを受けて関節をスムーズに動かすよう指令を出します。
この脳と関節との情報の往復が、神経回路の発達を促すのです。
リハビリの目的は、まず衰えた神経回路に刺激を与えて、脳と関節との情報のやり取りをスムーズにさせることにあります。
普段浮足で歩いている人には、足の指が動かない人もいます。しかし、足指を手でほぐしたり廻してあげたり、つま先立ちをして指に負荷をかけていると、いつの間にか指が動き出すというコトがあります。
これは筋力が発達したというよりも、指の神経回路に刺激が入り、再び機能し始めたことを意味するのです。
一般的には筋肥大は、神経回路の発達に遅れて起こります。
インナーは反射神経と連動している筋肉ですから、ここをチューブトレで効果的に鍛えることで、神経回路の発達を促し、それがアウターの筋肥大の成長も助けるのです。
関節がスムーズに動くようになれば、それはアスリートのパフォーマンスの向上につながります。
たとえばサッカー選手であれば、パスやシュートなどの精度が高まりますし、ボクサーなら狙ったところにパンチを打てるようになりますし、動きの”キレ”が高まることにもつながるでしょう。
運動前のウオーミングアップも短縮できる

木場トレーナーは、チューブトレは運動前や試合前のウオーミングアップの時間を、短縮させてくれる効果もあるといいます。
チューブトレは関節の受容器を刺激して、関節の動きをスムーズにすると同時に、関節の可動域を広げてくれます。
可動域が広がることで、ウオーミングアップの際の手足の動きも大きくなりますので、その分だけ体が温まる時間も短くなります。
木場さんによれば、冬場の寒い時期に、ランニングやストレッチでウオーミングアップさせようとすると、大体合わせて30分程度かかってしまうといいます。
しかしチューブトレなら、その半分以下の時間でアップを完了させられるのです。
またチューブの良さは、場所をとらないので室内でもアップできるということです。
アップするときは、一般的に動的ストレッチと呼ばれる、身体を動かしながらのストレッチ法を利用することが多いのですが、手足を大きく伸ばしたり動かしたりするので、室内だと不都合な場合が多いのです。
チューブトレの場合は、チューブで動きをある程度制限しますので、力を入れて手足を伸ばそうとしても、少ない範囲で済みますし、チューブの負荷で制御できるので、心置きなく力をいれることができます。
その意味では、チューブトレはストレッチと筋トレの要素を併せ持っているのです。
チューブの適切な使い方
チューブの適切な使い方を、簡単に紹介します。
チューブの位置ですが、この本で使う位置は、ひざの上と足首の2か所です。
ひざに直接つけるのは、動きを制限しケガにつながりかねないのでやめましょう。
足首については、くるぶしの上を目安にしてつけてください。
次に、チューブトレでは、必ずつま先とひざの向きを同じ方向に向いているようにしてください。
ヒザとつま先が同じ方向を向き、脚が一本の棒になるようなイメージを持ちながらトレーニングしよう。
そうでないと、ひざとつま先が違う方向を向くと、ひざがよじれて負担がかかり、ケガの原因になります。
そして、ここが一番肝心なのですが、チューブを引っ張ることではなく、身体の軸を意識するようにしましょう。
チューブトレーニングの狙いは、チューブを引っ張ることで脚力をつけるのではなく、引っ張った状態でもカラダがぶれないような軸を支えることにある。したがって、チューブを強く引っ張るよりも、カラダの軸をぶらさないことに意識を集中させて、ゆっくりと丁寧におこなおう。
チューブを引っ張ることに意識が行ってしまうと、身体の軸がぶれてしまって、結局負荷は逃げて行ってしまいます。
この本は、チューブを使ったさまざまなトレーニング法を紹介してくれていますので、チューブトレーニングを自分の目的にあった形で取り入れていってほしいと思います。
チューブトレの良さは、老若男女、年齢や性別関係なく、だれでも自分の目的に合ったトレーニングが用意され、効果が期待できるトレーニング法ですので、この本の方法を一通りマスターできれば、あとはいくらでも応用が利きます。
また実際の動きをより視覚で確認するには、木場さんがわかりやすい指導を動画で見せてくれていますので、参考にしてください。
また、木場さんはあのサッカー日本代表の長友選手をモデルにした体幹本も監修されていますので、そちらも参考にしてください。