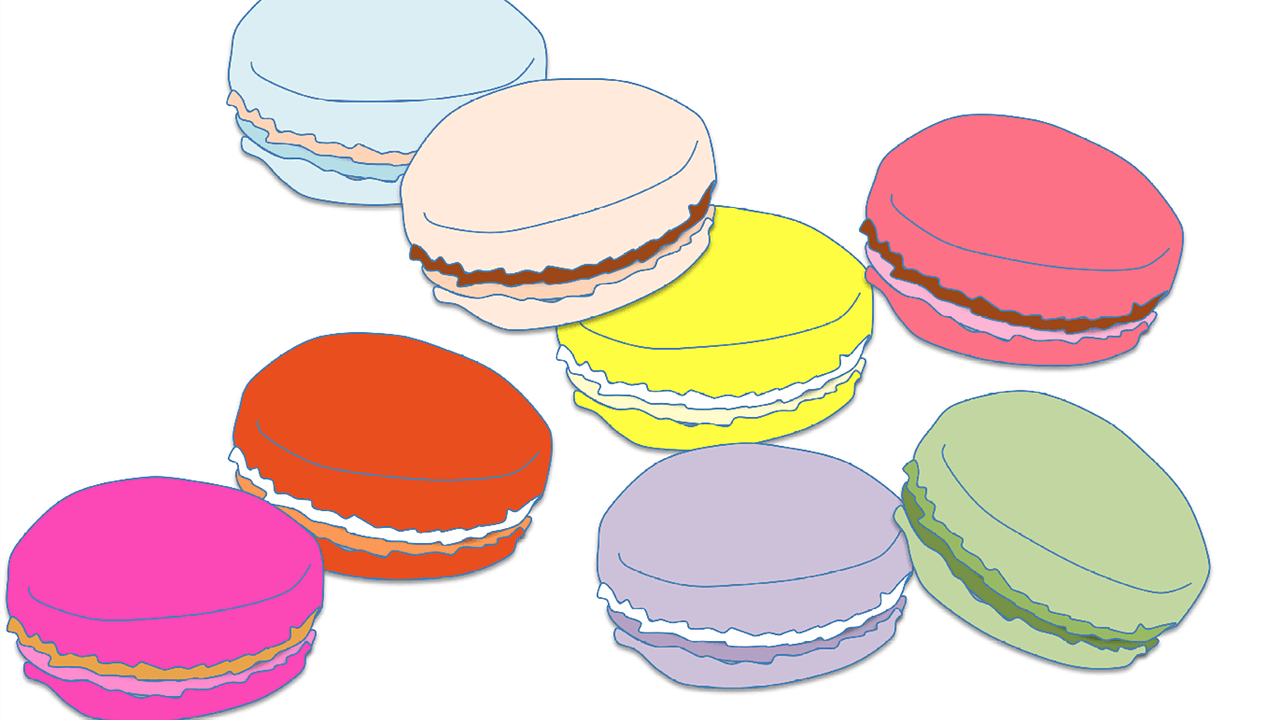Contents
『江部先生、「糖質制限は危ない」って本当ですか?』 江部康二著 洋泉社

ダイエットに糖質制限がいいというのは、パーソナルトレーニングで有名なライザップなどの宣伝によって、かなり人口に膾炙するようになってきたと思います。
糖質ダイエットというと炭水化物以外はそれなりの量を食べられるので、空腹感に悩まされずに成功しやすく、また即効性があるので短期間で痩せられるダイエットとして人気があります。
そういうといいことずくめのようですが、糖質制限には大きなデメリットがあると主張される識者の方も多いです。
今回紹介する江部康二先生は高雄病院の理事長で、日本糖質制限医療推進協会理事長でもある糖質制限医療の第一人者です。
江部先生は糖質制限ダイエットを擁護する立場から論陣をはってきました。
この『江部先生、糖質制限は危ないって本当ですか?』は数々の糖質制限ダイエットへの批判に先生が反論する形で糖質制限のメリットを解説するものになっています。
糖質制限バッシングに反論する
長期間の糖質制限は健康にダメージがあるのか
糖質制限を5年以上続けると死亡率が高まるという話があります。
これはアメリカの科学雑誌「プロスワン」誌に掲載された能登洋氏の論文で主張されたものですが、この論文自体の評価は専門家の間では高くはありません。
この論文は429の先行論文から9つの論文を選び出しこれをメタ分析したものです。
その分析結果は、総摂取比率で糖質摂取量が30~40%のグループと、60~70%のグループを比較して、前者のGの死亡率は後者のGの1.31倍になったというものです。
しかしこの9つの論文の中にはエビデンスの信頼度が低いものも混じっており、結論の信頼度も低いものです。
この主張が人口に膾炙したのは、2013年に朝日新聞に「長期の糖質ダイエットは危険?」というこの論文を対象にした記事が出たからです。
しかしもともとの論文の結論の信頼度が低いわけですから、新聞記事の内容を信じる必要はないのです。
肝硬変、膵炎、腎不全の人は注意が必要
仁部先生も糖質制限がどなたにも有効で健康に害がないと考えているわけではありません。
肝硬変が一定の範囲を超えて進行している患者さんは糖新生の機能が低下している可能性が高く、低血糖に陥る危険性がありますので糖質制限はよくありません。
糖新生というのは、糖質以外のエネルギー源を脂質やアミノ酸=たんぱく質を肝臓や腎臓で分解して求めることをいいます。
また糖質制限をすると相対的にも絶対的にも脂質の割合が高くなりますから、低脂肪食が推奨される活動性膵炎の場合は糖質制限は控えなくてはなりません。
腎臓に問題がある場合は、お医者さんの判断を仰いでたんぱく質制限が必要かどうかを決める必要があります。
上記のような疾患以外の人で肥満などの生活習慣病を抱えておられる人は、糖質制限は有効な食事法になります。
高脂質の食事は心臓病になるのでは?

糖質制限をすると代わりに脂質摂取量の割合が自然と大きくなります。
そのためそのような高脂質な食事が肥満を逆に導くのではないかという疑問があります。
これについて江部先生はアメリカでは脂質を減らして糖質を増やした時期に肥満率が倍増したというデータを挙げてこう言います。
食事で摂った脂質がそのまま中性脂肪として血中に残りつづけるのではなく、ほとんどがいったん脂肪酸とグリセロールに分解されるのです。人間の身体は食事で脂質をたくさん摂れば、それだけ血中の資質の状況が悪くなる、といった単純なシステムにはなっていないということです。
中性脂肪となるのはあくまでもエネルギーとして利用されなかった余剰分だけで、血中の中性脂肪を増やしてしまうのは別の原因によるものだといいます。
それが糖質の摂りすぎです。それではなぜ糖質の過剰摂取は肥満を促進させるのでしょうか。
それはインスリンの追加分泌です。
インスリンは中性脂肪を脂肪細胞にためやすくする作用があります。
このため糖質の摂取が増えれば増えるほど、脂肪細胞や肝臓に中性脂肪がたまりやすくなるのです。
僕は肥満だったときに脂肪肝の症状が出ていたのですが、お肉や脂身をそれほどとっていた印象はなく、お菓子やお米など炭水化物を中心に過剰摂取していた実感がありました。
なので脂肪肝といってもそれは脂質の摂りすぎから来たのではなく、明らかに炭水化物つまり糖質からでした。
そして昔はいざ知らず、最近の脂肪肝患者さんの多くは脂質からではなく糖質からなっていると思われます。
これは食にかかわる環境の変化が大きいと思います。
コンビニなど家からちょっと歩けばスイーツやおにぎりなど炭水化物を手軽に購買することができるようになっています。
炭水化物は加工しやすく大量生産しやすいので安価で商品化されやすいのです。
日本人が毎日ステーキを食べ過ぎて脂肪肝になるというのはちょっと考えにくいですよね。
糖質制限でコレステロール値が上がるのではないか
糖質制限で脂質の割合が相対的に上昇するとコレステロール値が上昇して心疾患にかかりやすくなるのではないかと心配される方もいます。
しかしこれはコレステロールが敵視されていた一時代前の認識からきています。
人体はたんぱく質、脂質、無機質、水分の主要成分で構成されています。
特に脳は乾燥重量の65%が脂質であり、その脳脂質の25%がコレステロールでできています。
これでコレステロールというものが人体に欠かせない成分であることがわかるでしょう。
さらにコレステロールは細胞膜の成分でもあり、男性ホルモン、女性ホルモンの成分でもあります。
コレステロールには善玉コレステロールと悪玉コレステロールがありますが、これは働きの違いを表しているだけで、悪玉が悪いということではありません。
善玉は血中に余ったコレステロールを肝臓に回収させる働きを、悪玉は末端の細胞組織にコレステロールを運ぶ役割をしています。
なのでどちらのコレステロールも人体には必要なのです。
つまり総コレステロール値が高くても動脈硬化にはならないということになります。
糖質制限をすると筋肉量が落ちてしまうのではないか
糖質制限をすると糖新生によって筋肉=たんぱく質が分解されてしまい、筋肉量が減ってしまうのではないかという話があります。
しかし江部先生はこれは誤解だといいます。
どのような食事をしている人であっても、毎日一定量の筋肉の分解と再生は起こっています。
このとき全身の筋肉量が減るか減らないかは糖質の摂取量とは無関係です。
人体においてエネルギーが使われる優先順位は決まっているといいます。
アルコール→ブドウ糖やグリコーゲン→脂肪酸やケトン体→アミノ酸
これが意味しているのは、カロリーの摂取量が不足していない限り、糖質や脂質がまず使われるわけで、たんぱく質の利用は最後になるということになります。
つまり、
糖新生によって人体の筋肉量が減るという事態は、極端な低カロリーや低タンパク状態が長期間続いて、蓄積されていたグリコーゲンと体脂肪を使い果たした後ということになります。
糖質制限ダイエットするような方は体脂肪はたっぷりと持っているわけですから、まず体脂肪がなくならない限り、筋肉が分解するようなところまではいかないと考えられるのです。
低糖質食はほかの食事法を比較しても優れているのか
生活習慣病を改善する食事法というと最近までは低脂肪食が主流でした。カロリー制限と低脂肪食で体重を減らすということが食事療法の基本でした。
そこに最近は低糖質食が出てきたのわけです。
また地中海食というオリーブオイル、ナッツ、魚介類、果物を中心とした食事法も最近は注目されています。
そこで低脂肪食と低糖質食と地中海食を比較してどれがが減量や心血管疾患に対して有効なのかについての研究の結果を紹介したいと思います。
これは低脂肪食と地中海食についてはカロリー制限を併設していますが、低糖質食にはそれがありません。
その食事法を実践した3グループの体重の変遷をグラフにしたのがリンク先の日経ウーマンの記事糖質制限に低脂肪・・リバウンドしないのは?2年の記録のグラフです。
これは江部先生が紹介しているものと同じです。これをみると一番体重の減少幅が大きいのは低糖質食です。
低糖質ダイエットは短期間での即効性があるといわれますが、このグラフはそのことを裏付けています。
ただしその後のリバウンドによって低糖質食は地中海食と並びます。
これに対して低脂肪食と地中海食の減量率は同程度だといえます。ただしその後のリバウンド率をみてみると、低脂肪食が大きくリバウンドしているのに対して地中海食はそれほどリバウンドしていません。
これは地中海食は低脂肪食とちがってそこまで肉類や油を制限するような食事法ではないため、我慢の度合いが低脂肪食より少なくて済むからだと思います。
こうしてみるとダイエットという観点からは低糖質食がほかの二つに比べて短期的に優れているといえそうです。
長期的には低脂肪食より優れているものの、地中海食よりもリバウンド率は高く、長期的には地中海食とどっこいどっこいという評価になるでしょう。
低脂肪食や地中海食の詳しい内容はほかの記事ロカボ低糖質ダイエット以外にも目を向けるで紹介していますのでそちらを参考にしてください。
福岡県久山町で失敗した糖尿病食
江部先生が高糖質食と糖尿病の発症率の関係を日本のデータでみた事例を紹介しています。
これは九大医学部が行った研究で、久山町は人口8000人の小さな町ですが、5年ごとの健康診断の受診率が80%を超え、死亡後の解剖検査も82%を超えるという地域なために、成人検査の研究対象としてモデルとなる地域となっています。
1960年代初め、高血圧による脳卒中の発症率の高さが社会問題となっていました。
久山町では全住民に対して減塩などの食事指導を行い、また降圧剤治療も行うことで、脳卒中の発症率を3分の1に激減させたのです。
その実績を踏まえ次に糖尿病の発症率改善に乗り出しました。
これは1988年に始まり、食事療法と運動療法を併せた指導を行いました。
食事指導は食事の栄養素の割合を、「糖質60%、脂質20%、たんぱく質20%」にするということです。
特徴は一言でいうとカロリー制限高糖質食ということになります。
そしてその結果ですが、実は糖尿病発症率を減らすどころか増やすことになったのです。
1988年に男性は15%、女性は10%だったのですが、2002年ではそれが男性では24%、女性が13%と増加したのです。
さらに糖尿病予備軍をいれると、男性が60%、女性41%と激増したのです。
この数字はほかの自治体の数字と比較すると全国平均で1.5倍にもなってしまったのです。
主食をとらないと生きていけないという思い込みを捨てる

日本人は戦後コメの消費量を徐々に減らしてきました。しかし江部先生によればそれでも日本人はコメを食べ過ぎているといいます。
そしてそれは日本人が主食を食べないことにまだ不安があるからだといいます。
しかしイヌイットなどが生肉を主食とするように、欧米人がパンやパスタを主食とまでは考えないように、穀物を主食とする考え方は日本人独自のものだといえるといいます。
主食として穀物を食べないと生きていけないという考えは、惰性による先入観から来る誤解にすぎません。
確かに人類は1万年ほど前農耕を開始してから穀物を常食することにより、でんぷんを分解するアミラーゼという酵素を体内に育んできました。
これによって農耕民族の食後血糖値は狩猟採集時代よりも上がることになりました。それによってインスリンの追加分泌も大幅に増えたのです。
さらに18世紀になると今度は欧米で小麦の精製技術が開発され、小麦の消費量が上がりました。
ほぼ同時期に日本ではいわゆる精製された白米である「銀シャリ」がでてきました。
日本人の精製米の消費習慣はわずかここ200~300年であり、歴史的には新しい事象なのです。
ほぼ同時期に世界で糖質消費量があがり、インスリンの追加分泌量が人類規模で上がったのです。その規模は10倍から30倍になります。
明治時代の日本人は精製米を食べても大丈夫だったのではないかと思われるかもしれませんが、そのころの日本人は炊事洗濯家事労働と現代とは比べ物にならないぐらい運動量が多かったのです。
現代人のように家事の多くが機械化自動化され、デスクワークなどで座っている時間が大半になっているにもかかわらず糖質の消費量が上がっていては、糖尿病になるのも当然のことだといえるのです。
本書は2015年に出版されていて、比較的古い本になります。このためすでに販売中止になっています。
なので先生の考えが最新版で読むことのできる『江部康二の糖質制限革命』のほうをお勧めしておきます。