Contents
『体力の正体は筋肉』樋口満著 集英社新書

最近だるいなしんどいな、疲れやすいなと感じたら、その原因について考えてみましょう。
寝不足からきているのかもしれないし、仕事上のストレスからきているのかもしれません。精神的なものかもしれませんし、もしかしたら重篤な病気の兆候かもしれません。
様々な理由があるとおもいますが、実は大きな割合を占めるにもかかわらず気がつきにくい原因があります。
それが筋力不足です。
今回取り上げる著書は『体力の正体は筋肉』です。著者はスポーツ科学が専門の樋口満先生です。
年齢とともに現れる体力低下の正体
スポーツ選手の引退年齢は科学的なトレーニング内容の向上や栄養学の発展とともに年々伸びている印象があります。
サッカーの三浦知良選手やMLBのイチロー選手など、ひと昔では考えられなかった年齢のベテラン選手が現役生活を送っています。
とはいえやはり年齢とともに体は衰えていきます。
プロ野球選手の平均引退年齢は29歳といわれていますので、30歳にも届いていません。
もちろんこの年齢には実力が届かずに早期に引退された選手も多く含んでいるので、引退が年齢による衰えだけとはいえませんが、それでも30歳前には多くの選手が引退していくのです。
プロの野球選手という日頃必死に鍛え上げているアスリートでも体力の衰えから引退していくわけですから、一般人ならなおのこと何もしていない分だけその衰えは日常生活のなんでもないシーンにも表れてきます。
それでは一言で「体力の衰え」といっても、具体的にはどのようなことを表しているのでしょうか。
そもそも体力っていったい何?
樋口先生によれば、世間一般でいう体力というのは行動体力のことを指し、次のように定義されます。
体力とは、作業や運動といった身体活動に要求される潜在的な能力、身体的活動能力
そしてその身体的活動能力を支えるのが二つの要素です。
それが「筋力」と「全身持久力」です。
筋力とは骨格筋(骨格を動かす筋肉。内臓筋と対)が発揮する力のことで、その力はほぼ筋肉の断面積に比例します。
つまり筋肉が肥大化すればするほど、発揮する力はそれだけ大きくなります。
これに対して全身持久力とは、全身を使った運動を行った際にどれだけ長く続けられるかという能力のことで、一般的には”スタミナ”という言葉の範疇に入ります。
このため全身持久力は筋肉だけではなく心肺能力にも関係してきます。
そのため筋力を鍛えるには筋肉に刺激を与える筋力トレーニングが必要になりますし、全身持久力にはランニングなどの有酸素運動が必要になります。
この二つが重要視される理由の一つはそれが測定可能だということです。
体力がある体力がないといったときのような抽象的で曖昧さが残る表現ではなく、計測ができるというところが筋力と全身持久力の素晴らしいところです。
溝口先生にいわせれば、体力の正体とは筋力と全身持久力ということになります。
筋量のピークはいつ?

皆さん、全身の筋肉量は体重の何%を占めるのかご存知でしょうか。
成人男性の場合は40~45%、女性の場合は30~35%になります。
これだけの重量を占めるエンジンがさびついてしまうと、体が動かしずらくなったり、何をやろうとしてもすぐに疲れてしまうのはある意味当然のことだといえるでしょう。
エンジンがさびるというのは、年齢とともに筋繊維の断面積が減るということです。
この筋繊維の断面積というのは、
男性の場合は、上半身、下半身ともに筋繊維の断面積が1年間で増える量は12~13歳でピークに達し、18歳ぐらいまで増加の傾向がみられます。女性の場合は、14歳以降増えるペースは穏やかになるため、14歳ごろから男女の差は顕著になります。
それでは筋量のピークは20歳前ぐらいかというと、筋繊維の配列や大脳皮質からの刺激などほかの要素が絡んでくるため、断面積のピークと筋力のピークにはずれが生じます。
このため筋力のピークは、
男性は20~30歳、女性は20歳ごろで、40歳ぐらいまではピークのレベルがなんとかキープされるのが一般的です。
ということは普段になにもしないと、運動量の低下とともに筋量は若いうちからずっと落ち続けていくわけです。
樋口先生によれば何もしなければ早ければ30歳ごろから、毎年0.5~1%程度低下していくといいます。
なので30歳を過ぎて疲れやすいと感じたなら、それは筋力の低下からきている可能性が高いのです。
座りすぎが引き起こす大きなリスク
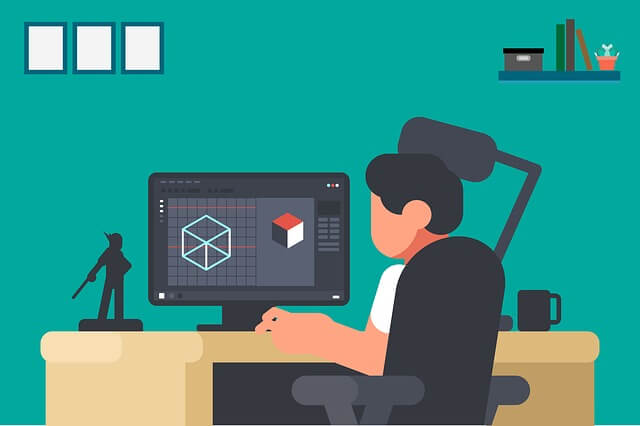
英語で”sedentary“という言葉があります。この”セデンタリー”の意味は「座っている、座りがちの、座っている仕事の」になります。
座りぎみの生活を”Leading a sedentary life”と表現します。このセデンタリーな生活を世界一送っているといわれるのが日本人です。
2011年にシドニー大学が世界20か国の平日の総座位時間数を調べたところ、日本人が1日あたりで420分(7時間)でトップになったのです。
座りすぎが健康に与える影響については分析が進んでいます。
座りすぎが健康に悪いということは知らなくても、エコノミー症候群という言葉は聞いたことがあると思います。
座りすぎというのは結局のところエコノミー症候群と同じです。日本人は飛行機に乗らなくてもエコノミー症候群にかかっているのです。
座っている間は下半身の筋肉は使われないので、下半身から送り返される血流は遅くなります。血流を心臓に送り返すスピードは座って30分で70%も落ちるといいます。
誤解しがちになりますが、健康に影響を与えるのは純粋に座っている合計の時間です。
運動をまとまった時間ほかでやっていても、座っている時間が長ければ健康に悪影響を与えます。
溝口先生はできれば20~30分に1回は椅子を離れて体を動かす、それができなくても最低1時間に1回はそうすべきだといいます。
下半身と体幹の筋トレで筋肉強化をはかる
それでは年齢とともに落ちていく筋肉量の低下を抑えるにはどうしたらよいでしょうか。
確かに筋肉量は何もしなければ落ちていきますが、筋肉自体は年齢にかかわらずトレーニングによって増強できます。
溝口先生は特に下半身と体幹の筋肉を鍛えなさいといいます。
筋力が低下しやすいのは、上半身よりも、下腿三頭筋、大腿四頭筋、ハムストリングスといった下半身の筋肉のほうが著しく、それが「老化は脚から」といわれる所以だと書きました。
それに加えて、大臀筋、腸腰筋、脊柱起立筋といった直立姿勢を支える筋肉も鍛えていく必要があります。
これらの筋肉を鍛える方法の一つがスクワットです。
スクワットは下半身筋トレの王様と呼ばれるぐらい定番のトレーニングのためバリエーションも豊富です。
普通のスクワットから、片脚だけでやるシングルレッグスクワット、体をより深く沈めるスプリットスクワット、体を倒して行うシシースクワット、ジャンプしながら行うジャンピングスクワットなどがあります。
ただしスクワットには欠点があって、それは地味なわりにきついトレーニングなので苦手に感じる人が多いということです。
上半身の筋トレは、例えば力こぶといわれる上腕二頭筋を鍛えるアームカールなどは、やった後は心地よい爽快感や充実感があるのですが、スクワットはあまりそういう実感がわきません。
このため筋トレを趣味にしている人も、どうしても上半身を中心にやって下半身は後回しにしてしまうために、上半身だけが大きくなって下半身は細いままという体型になりやすいのです。
こういう体型をチキンレッグといいます。鶏の足は体と比較してとても細いからですね。
そのため専用のマシンを使ったトレーニングのほうが続きやすいという人もいます。
最強のトレーニング、ローイングマシーンの効果

筋力の維持や増強こそ体力を増やす方法だと説く溝口先生が特にお勧めするのがローイングマシーンを使ったトレーニングです。
ローイングマシーンというとボート漕ぎを模したエクササイズマシンです。
ローイングマシーンの効能は筋トレと有酸素運動を併せてできることです。
このマシンはアメリカでは人気があるマシンの一つなのですが、日本ではあまりジムでもみかけないマシンです。
この違いはおそらくは住環境にあると思います。日本だとどうしても部屋が狭くてローイングマシーンのような横長にスペースをとるマシンは置きにくいのです。
だからこそフィットネスジムなどにはもっと置いてほしいのですが、残念ながらあまりみかけません。でも最近は置くところも出てきてるようです。
もう一つの理由はボート競技が日本よりもアメリカのほうが盛んで身近にあるということでしょうか。
アメリカの映画やドラマをみてると、結構ボート競技のシーンが出てきます。
僕が最近見たドラマだと『ハウスオブカード』というホワイトハウスを舞台にしてアメリカ政界の権力闘争を描いたものがあります。
ケビン・スぺイシーが大統領役ででてくるのですが、その大統領が自宅で木製のウオータータンクを使ったローイングマシーンを漕くシーンが頻繁に出てきてとても印象的でした(下の動画)。
ローイングマシーンが鍛える筋肉
ローイングマシーンが体力を向上させるのはレジスタンス運動と有酸素運動を併せ持っているからですが、それに加えて刺激を与える筋肉の範囲が広いことがあげられます。
ローイングによって、鍛えられる筋肉は、腕、体幹、脚など全身の筋肉の実に70%にも及ぶといいます。
溝口先生によれば、ローイングエクササイズをすることで、特に体幹部と大腰筋と腹直筋が発達するといいます。
ローイングは両足を伸展させた時(フィニッシュフェーズ)と、屈曲させたとき(リカバリーフェーズ)に使う筋肉が違ってきます。これがローイングが広範囲な筋肉を使える理由です。
両足が伸展するフィニッシュフェーズのときは脊柱起立筋などの主に背筋群が、屈曲するリカバリーフェーズでは腹直筋や大腰筋などの体幹屈曲筋が主に使われるのです。
このローイングのエクササイズを1分間に20回程度、それを5分間2セットずつか、10分間1セットやることで、大きな筋力増加が見込まれるのです。
ローイングマシーンの種類
実際のところローイングマシーンを使って本格的に筋力増強を図ろうとすると、それなりに本格的なマシーンが必要になります。
日本の住環境だと場所をとってしまうので、あまり現実的でないことは確かです。
ローイングマシーンは仕様に応じて値段も変わってきます。
数万円で手に入る油圧式は、コンパクトで置き場所には困りませんが、何分力のかかる方向が一定の上負荷も高くないためすぐに限界が来るのと、飽きてしまいやすいという特徴があります。
少し高くなると磁気方式というのもあります。磁気方式になると取っ手にひもがつくようになります。
ただ油圧式と同様に負荷のかかり方が一定でおもしろみがないこと、あるまとまった時間行うと回転部分が熱を持ち、一定の時間休ませないといけなくなるという欠点があります。
そこであくまでも置けるスペースが確保できるという前提でおすすめするのは、空気圧でフライホイールを回す方式です。
大学のボート部やハイアマチュア競技者、そしてジムに置かれているタイプはこの方式になります。
この方式がいいのは負荷のかかり方が本物のボートを漕いでるように自然だということです。
漕ぎはじめに一番負荷がかかり、足が伸び切る最後の方になると負荷がかからなくなっていくというような、オールでこいた場合に体感する”本物”に近い負荷のかかり方になることです。
このため飽きにくく、足から体幹、腕にいたるまで満遍なく強度のある負荷がかかりますので、しっかりと関連の筋肉を鍛えることができます。
この空気圧方式で有名なのは、アメリカのメーカーがつくるローイングエルゴメーターです。
この空気圧方式よりも上位の機種が先ほど動画でも紹介した水流式のローイングマシーンです。
水流式が空気圧とちがうのは漕いだ時に出る音です。水の入ったポンプを回すので、その際水が流れる音がします。
この音が実際のボートをこいだとき水面をかく際に出る音に近いので、本当に水面上でボートを漕いでいる気分にさせてくれるのです。
筋トレ、ワークアウトの効果は疲れにくくなること
筋トレやワークアウトの効果というと単純に筋肉がつくことで体が引き締まって見えたり、パンプアップした肉体により男らしくみえたりするなど容姿がよくなるということがよく上げられます。
しかし筋トレをするとそれ以上に実感するのは疲れにくくなることです。特に普段から疲れやすいと感じていた人ならその効果はてきめんに実感できることでしょう。
筋トレをすると筋肉が増大して体が大きくなったり引き締まったりするのにはそれなりの時間がかかります。
しかし疲れにくくなるという効果に限って言えば、割合早く出てきます。僕の経験上、1~2か月もすれば体調の向上は実感できます。
これは筋肉量が増えたことによる単純なパワーアップによるものというよりも、筋トレの過程で筋肉に負荷を与えたり、筋肉の収縮運動を繰り返すことによる血流やリンパの流れの改善、さらには成長ホルモンの分泌が増加するなどの複合的な効果の結果だと思います。
大体半年ぐらいトレーニングを続けると、個人差はあるものの次第に体が大きく固く強くなっていくのがわかります。
そうなると実際のパワーもついてきて、何をするにも筋肉の力で効率的に処理していけるので、相乗的に疲れにくくなっていくのです。






