Contents
『小さな習慣』スティーブン・ガイズ著 ダイヤモンド社

表紙がとってもかわいいので、一見軽いライフハック本(失礼!)に見えるかもしれませんが、なかなかどうして、脳科学に関する話題にページが多く割かれたちょっと硬派な本でもあります。
この本『小さな習慣』も、ダイエットコラム(小さな習慣からマシュマロテスト、キーストーンハビットまで)でも紹介した『習慣の力』も、かなりのページを割いて、脳と習慣との関係を語っています。
どうやら日本の習慣本の多くとは違って、アメリカの本は科学的な裏付けを志向する側面が強いようです。
日本の習慣に関する本では、個人の成功体験に読者の関心が集まるのに対して、アメリカの読者は個人の体験にとどまらない、汎用性のある習慣化メカニズムを求めているのかもしれません。
週刊文春の書評によると、担当編集者が原本のビジネス然とした表紙を、日本語訳では今のようなかわいらしい表紙に変えたそうです。
原本は下にありますが、原題は”Small Habits”ではなくて”Mini Habits”なんですね。副題は「小さな習慣、大きな成果」となっています。

このような編集上の変更も、日本人読者とアメリカ人読者の志向の違いを表しているような気がします。
脳の抵抗をいかに回避するか
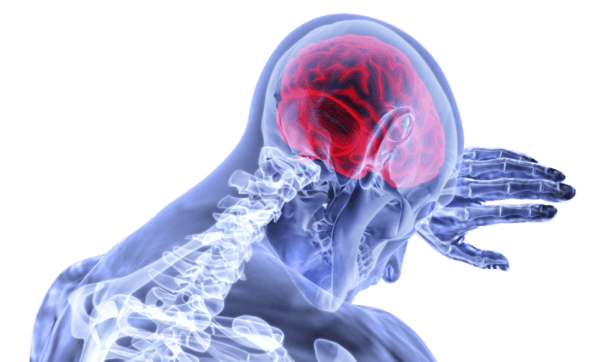
ガイズによると、習慣化のためには、脳の二つの機能を理解しておく必要があります。
一つは潜在意識をつかさどる部分で、もう一つは意識をつかさどる部分です。前者は脳の大脳基底核に、後者は前頭前野の部分にそれぞれ対応しています。
そして、脳に変化を与えるのは二つの要素です。
それは、”繰り返し”と”報酬”です。
脳は毎日大量のエネルギーを消費しています。そのエネルギー消費量はカロリー摂取量の約2割にあたり、この数字は身体全体の筋肉の基礎代謝量とほぼ同じです。
プロの将棋士が対局の合間におやつを食べるときがありますが、皆さん結構な大きさの大福やケーキを召しあがります。これは対局に使う脳の糖エネルギー消費量がそれだけ大きいからですよね。
脳はエネルギーの大飯ぐらいなわけですから、すぐにエネルギー不足になります。
このため脳は活動してエネルギーを消費するときに備えて、平時はスリーピングモードに入ってできるだけエネルギー消費をセーブしようとします。
脳がスリーピングモードに入っているときは、大脳基底核の部分が意識の水面下で働いています。
この大脳基底核が働くのは脳が繰り返し作業をしているときです。脳に刻まれた一定のルーチンを自動的にこなすときに大脳基底核は働くのです。
これに対して脳が活動しているときは、前頭前野が働いているときになります。
前頭前野は脳が変化と報酬を求めて新しい作業を求めているときに働きだします。前頭前野は大脳基底核が動かしている自動ルーチンをいったん止めて、代わりに新しいルーチンを導入しようと動き出すのです。
つまり、
大脳基底核→潜在意識→繰り返しを好む→エネルギー消費をセーブ
前頭前野→意識→報酬と変化を好む→エネルギーを消費する
人間は実に行動の45%を習慣で行っているといいます。つまり活動の半分近くは大脳基底核が働いていて、脳が自動化処理を行っているのです。
ジョブズもザッカーバーグも服装はいつも同じ
アップルとフェイスブックの創業者であるスティーブジョブズとマークザッカーバーグは、毎日着ている服装が同じことで有名です。
ジョブズは黒のタートルネックにジーパンでおなじみですね。ザッカーバーグは同様にグレーのTシャツにジーパンです。
ちなみにこのタートルネックはイッセイミヤケらしいですが、一般には販売されていません。ジョブズは特注で300着を一括で注文したそうです。
なぜ毎日決められた同じ服装をするかというと、一説には服選びに貴重な判断力を使いたくないからだそうです。
彼らは毎日とんでもない額が動くプロジェクトの是非を頻繁に判断していかなくてはならないので、それ以外のところに脳の貴重なエネルギーを使いたくないのです。
ガイズは1996年に行われたラディッシュ実験というものを紹介しています。
67人の被験者をある部屋の中に入れ、そこにチョコレートやクッキーを持ち込みます。
ただしそこでチョコやクッキーを食べられるのは一握りの人に限定されています。残りの人は代わりに生のラディッシュ(ハツカダイコン)のみ食べることを許されます。
多くのチョコやクッキーを食べられない人は物欲しそうにそれらを眺めるだけです。
そのあと二つのグループはそれぞれパズル問題を解かせられます。その結果、ラディッシュのグループの人が回答した数は、チョコを食べた人の数の半分以下だったといいます。
つまりラディッシュしか食べられなかった人は、パズルを解く意志を途中で失ってしまったようにみえます。
意志力とは枯れることのない力の源泉ではなく、使えばなくなってしまうものなのです。
自己管理の研究で、一日の早い時間にむずかしい決断をした人は、その後は誘惑に負けやすくなり、自制心が低下するとわかりました。
そしてそのことを知っている上記のリーダーたちは、その力を大切な意思決定のためにセーブしているのです。
選んだ習慣をばかばかしいほど小さくする

このように脳はエネルギー消費を要する大きな変化をあまり好みません。
できるだけ大脳基底核で情報を処理してスリーピングモードのままでいようとします。
なので新しい習慣を導入しようとすると脳は変化を嫌がって抵抗します。これが新しい習慣を導入しようとしても失敗する理由です。
それでは脳の抵抗をいかにすれば回避できるでしょうか。
それは脳がびっくりしない程度の小さな変化をそろりそろりと導入することです。
習慣化は先ほど述べた脳の構造から最初の段階が一番難しいのです。なので小さな小さな習慣を静かに導入する必要があります。
それではどのくらい小さくすればいいのかというと、ガイズはこういいます。
”ばかばかしいほど小さい”と声に出して言ってみれば、その行動が本当に小さなステップかどうかがわかるでしょう。
ガイズは例えば毎日腕立て100回したいなら腕立て1回にチャレンジにしよう、毎日ポジティブに生きたいなら1日2つポジティブなことを考えようといっています。
自分もストレッチを習慣にしようと思った時はとりあえずヨガマットを床に敷いてみることを目標にしました。
マットを床に敷くというのはストレッチしたことにはならないだろうって思ったかもしれません。
もしそう思えたなら続けられること請け合いです。
そしてせっかくマットレスを敷いたのだからちょっと寝転んで身体を伸ばしてみようかなと思うようになります。そうなると次のステップにはいります。
マットに寝て身体を伸すと誰もが気持ちいいと感じるはずです。気持ちいいということは脳が快感を得て喜んでいるということです。
このステップまで行けば脳は一連のルーチンをやれば快感が得られることを学習します。
そしてこの一連のステップが脳の大脳基底核と前頭前野それぞれに対応しているのです。
つまり、
1.毎日ヨガマットを敷く→大脳基底核に繰り返しルーチンをおぼえさせる
2.せっかくだから寝転んでみる→目標を小さくして物足りなさを感じさせる
3.身体を伸ばすと気持ちがいい→前頭前野に快感の報酬を与える
ちなみに今の自分はストレッチの気持ち良さを脳でおぼえこんでいるので習慣化できています。
ストレッチをやらないと身体がだるくてなんだかムズムズします。ストレッチをやらないと気持ち悪くなってしまっているのです。
これは脳が快感を求めてストレッチをするよう身体に指令を送っている状態だといえます。
意思力とモチベーション、どちらが優れている?

人間何か新しいことを始めるときは、モチベーションの力に頼るというのが信じられてきました。
そのため”モチベーションを高く”というのは一般的に推奨されてきました。そしてそれがそう信じられてきたのは、繰り返しそう教えられてきたからです(まさに大脳基底核の働き!)。
しかしモチベーションには欠点があります。それは感情=やる気を基盤にしているためにいつも不安定だということです。
感情は不安、ストレス、体調、人間関係、仕事、プレッシャーなどによって左右されます。
モチベーションが一番高いのは始めるときです。始めた後は多少の変動はあっても徐々に低下していきます。
ガイズはこの現象を「熱意減退の法則」と呼んでいます。
このため不安定なモチベーションを習慣化の基盤にしている限り、失敗することは目に見えているといえます。
行動するのにモチベーションが必要だと信じることほど、危険な習慣はありません。
ガイズはモチベーションよりもほんの少しの意志の力を重視します。
先に行動するとモチベーションは後からついてくる
やる気がでない時でも嫌々始めてみるとなぜか徐々にやる気が出てきて、いつの間にか夢中になっていたという経験は誰しもあると思います。
サッカーの三浦知良選手はとりあえずやる気がなくてもスパイクを履いてみるといいます。小説家の村上春樹さんもとにかく原稿に書き出してみるそうです。
結構な数の成功者たちがその習慣を実践しています。
やる気が出ないときでも少しの意志の力で物事を始めてみる、これがモチベーションに頼ることなく意志の力で習慣を続けていく秘訣になります。
小さな習慣は自分を認めるトレーニング
習慣を小さくして導入することで、脳にさとられることなく変化を受け入れさせやすくなることがわかりました。
しかし小さな習慣の効用はそれだけではないのです。
小さな習慣を継続することで得られる小さな成功体験の積み重ねが、自分を信じる力、自己肯定感を生み出してくれるのです。
ガイズは自己肯定感を次のように定義します。
自己肯定感とは、自分には結果を引き出す能力があると信じることです。
この自己肯定感が少ない人は何をやるにしてもその成功確率を小さくしてしまいます。
自分はどうせ失敗すると思って物事を始めると、哀しいことに実際に失敗を引き寄せてしまうのです。
しかし小さな習慣は成功が約束されているルーチンです。やれることから逆算して習慣のレベルが設定されているからです。
小さな習慣は脳が好む二つの要素が獲得できます。成功体験の繰り返しとそれから得られる自己肯定感=報酬です。
小さな習慣は自分を認めるトレーニングでもあるのです。
*追記になりますが、小さな習慣のダイエット版の新刊が発売されるそうです。ダイエットを習慣にしたい方には朗報ですので、ここでも紹介しておきます。






