Contents
『成功をする人たちの起業術 はじめの一歩を踏み出そう』マイケル・E・ガーバー著 原田喜浩訳 世界文化社

この本「成功する人たちの起業術 はじめの一歩を踏み出そう」は世界的ベストセラーとなった、経営コンサルタントのマイケル・ガーバー氏の著作です。
この本の旧版は1988年に出版されたので、ずいぶん昔になりますが、今読んでもまったく内容の古さを感じさせないばかりか、むしろ現代においてますますその価値を高めているように思えます。
本書は2001年に装いを新たに、内容も一部変更して出版されたものですが、主人公はサラという女性で、パイを焼くことが得意で、ついにパイの専門店をオープンさせます。
しかし、美味しいパイをお客さんに提供したいという最初の意気込みはどこかにいって、今は毎日の雑用に疲れ果てて、パイを焼くことさえ嫌になってしまった状況にいます。
そこにガーバー氏がコンサルタントとして登場し、サラさんを指導していくというお話形式になっています。
なぜ、意気揚々とお店を開いたサラさんが、今では疲れ果ててしまったのか。その大きな原因の一つが、サラさんがその他大勢の個人事業主と同様に、職人タイプの事業家であることです。
3つの人格バランスをチェックしなおそう

ガーバーは、事業成功のためには三つの人格のバランスを考えることが必要だといいます。
三つの人格とは、起業家、マネジャー、職人です。
起業家とは、理想家であり、イノベーターであり、ビジョンを持っていて、未来に住む人でもある、本質的な戦略家といえます。
起業家の人格とは、私たちの中の創造的な部分である。未知の分野への取り組み、時代を先取りした行動、わずかな可能性への挑戦、こんな無理難題に対して、起業家の人格は最高の能力を発揮する。
起業家がいなければ、世の中は既存の大企業ばかりになってしまうはずです。
次にマネジャーですが、マネジャーとは管理が得意で、事業に秩序を与えてくれる実務家です。
マネージャーがいなければ、組織はたちまち混乱して、計画さえ立てられなくなってしまうでしょう。
最後に職人ですが、職人は自分の手でより良い商品をつくりあげることを目標にしているタイプです。
その意味では、職人は個人主義者で、組織とは本来あまりなじまないタイプです。
起業家が未来を生き、マネジャーが過去を生きているとすれば、職人は現在を生きる人である。モノに触れて、つくりあげることが大好きで、決められた手順に従って仕事をしているときに、幸せを感じるのである。
どのような人でも、事業を始める限り、この3つの人格を内に持っていますが、その割合は人それぞれです。
しかし一般的には、何かをやり始めるのは自分が修業した分野であることが多いと思いますので、職人タイプの人格が支配的なものになっている人が多いでしょう。
実際、バーガーの経験上でも、起業家タイプはせいぜい10%程度で、マネジャータイプも20%、残りの70%が職人タイプだといいます。
職人タイプが事業を始めると、他の二つの人格が職人の邪魔をすることが往々にしてあります。
職人はそのことにいら立ち、ストレスを感じ、いつの間にか疲弊してしまうのです。
バーガーは、せっかく事業を始めても嫌になってしまうのは、この3つの人格のバランスの悪さが関係しているといいます。
なので、一度この人格バランスを見直すことが必要になるといいます。
ほとんどのケースで、職人によった人格配分を、起業家もしくはマネジャーのほうにもっと寄せていく必要があるというコトになります。
商品を売るのではなく、事業を売る

バーガーは、職人タイプは”商品”を売ろうとしてしまうが、起業家タイプは”事業”を売っているといいます。
職人が商品の先にみているのは自分自身です。職人は自分が満足するような商品を、自分の手で作ろうとします。
自分が満足できない商品は売りたくありませんし、自分が満足できる商品で売れない場合は、顧客に見る目がないと考えるのです。
起業家が見ているのは顧客です。起業家は、顧客が満足するような商品やサービスを、自分の事業が提供できているかを常に意識しているのです。
職人が商品を自分に合わせようとするの対して、起業家は商品を顧客に合わせようと努力します。
「顧客は私の事業をどう思っているのだろうか。私の事業は競争相手と比べて、どれくらい差別化できているのだろうか?」という問題意識を起業家は常に持っている。
そのために、起業家は自分の顧客像をはっきりさせなければなりません。
バーガーは、起業家ははっきりとした顧客像を持てない限りは事業の成功はおぼつかないといいます。
このように事業を始めるにあたって、職人と起業家では大きな違いが存在するのです。
職人タイプが事業を成長させるためには、内に眠っている起業家の人格を刺激して表出させないといけません。
それが、ガーバーのいう「事業発展プログラム」なのです。
目指すのは事業のパッケージ化
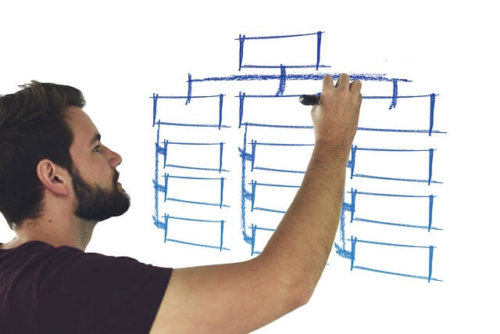
バーガーは、起業家は事業そのものを売っているのだといいました。
そうであるならば、事業そのものが売れるような状態にしなければなりません。
そのためには、事業をパッケージ化する必要があります。
このようなパッケージ化に最初に大成功したのが、あのハンバーガーショップのマクドナルドだといいます。
ガーバーもマクドナルドを引用して評価しています。マクドナルドは自社を「世界で最も成功を収めたスモールビジネス」といっているぐらいです。
マクドナルドはマクドナルド兄弟が始めたのでこの名前がついているのですが、このマクドナルドを単なるハンバーガーの個人ショップから、今のような世界的な飲食チェーンにしたのは、この店をたまたま訪れた52歳のセールスマンのレイ・クロックです。
クロックはマクドナルド兄弟が従業員とともに、効率よく、品質のばらつきもなく、どんどんハンバーガーをつくっていく様子をみて、衝撃を受けたといいます。
マクドナルド兄弟がつくりあげたのはハンバーガーショップではない、お金を生み出す機械だ!
クロックは、マクドナルド兄弟を説得(だまして?)して、12年かけてマクドナルドのフランチャイズ権を獲得したのです。
ここら辺のストーリーをおもしろおかしく、そして冷酷に描いた映画が、『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』なのですが、自分もこの映画の大ファンです。
クロックは、マクドナルドをフランチャイズ化して、つまりは事業をパッケージにして、世界中にハンバーガーではなく、ショップ自体を売ったのです。
レイ・クロックは、「何を売るか」ではなく、「どのように売るか」に注目した。つまり、売るための仕組みにこそ価値があると考えたのである。
この事業をパッケージにして、事業そのものを商品化するためのプログラムが、ガーバーが提供する事業発展プログラムなのですが、その詳細については、ぜひ本書を読んでほしいと思います。
簡単にその内容を言えば、あなたの今の個人商店を、まるで一流企業になったつもりで経営するための仕掛けづくり、システム化のためのプログラムなのです。
一流企業は名もない会社であったころから、一流企業のような経営をしていたからこそ、一流企業になれたのである。
事業発展プログラムは、経営者自身がマネジャーのように管理し、職人のように自分で商品をつくらなくても、会社がまわっていくシステムをつくるために導入されるのです。
そのためには、現場の知恵をマニュアル化して、誰がやっても同じように効率的に業務が遂行できるようにしなければなりません。
自分のお店を、将来成長させて売却するための試作モデルにすることが、プログラムの目的なのです。
無印良品と共通する仕組みづくり
こうやって、ガーバー氏のプログラムを見てみると、以前記事にした無印良品のMujigramとの共通性を感じずにはいられません。
ガーバー氏の事業発展プログラムが起業する際に事業の試作モデルをつくる際のテンプレートになっているのに対して、無印のMujigramは落ち込んだ会社を立て直し、成長軌道に再び戻す際に使われたという違いはありますが、目指すところは同じです。
つまり、経営者が現場にいなくても、優秀な店長がいなくても、会社が自然と回っていく仕組みをつくろうということになります。
ガーバー氏は、個人店がフランチャイズを目指さなければならない、と言っているのではないといいます。
経営者がいつまでも現場にしがみついていないと回らないようなお店では、遅かれ早かれ、いつかは破綻してしまうということは意識しておかなければならないといっているのです。
そのためにはマニュアル化できるところはマニュアル化して、誰がが来てもすぐに仕事ができるようなシステムづくりを、普段から心がけておかなければならないのです。
そうしなければ、仕事が属人的なものになり、サラさんが苦労したように、優秀な人が抜けたら事業がまわらないようになってしまうからです。
この本は対話形式なので、コミック版によく合っています。ビジュアルで読みたい方は、コミック版もお勧めです。






