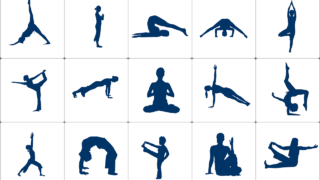『集中力はいらない』森博嗣著 SB新書

集中力があるというのは一般的にいいように使われますし、集中力がなくて困っているという悩みは誰にでもあると思います。
自分も昔は多少あったように思いますが、最近は年齢のせいもあり、その集中力も続かなくなってきたように感じます。
この本『集中力はいらない』は、ミステリー作家で有名な森博嗣さんが書かれたものですが、一般的に評価されがちな集中力よりも、あちこちに思考が分散し展開していくような”分散力”のほうを評価するという視点で書かれたものです。
森博嗣さんはいわゆる理系作家として有名で、『すべてがFになる THE PERFECT INSIDER』などのミステリーシリーズなど自分も大好きで、どちらかといえば文系タイプの自分としてはそのものの考え方や思考力にあこがれるところがあります。
ミステリーなどは難しいトリックを考えないといけないので、ミステリー作家はすごいなあとあこがれていたのですが、森さんに言わせると、ミステリーは謎解きのフレームワークにはめればいいので書きやすいといいます。
実際森さんはほとんど小説を読まないそうですから、いわゆる私小説的な小説とミステリーを書くというのは、まったく違うアプローチなのかもしれません。
集中しない力がアイデアを生み出す

今ではPC上でのマルチウィンドウという言葉も当たり前になりすぎて、逆に使われなくなったぐらいですが、ネットサーフィン好きなひとはいろいろなサイトにアクセスしながら、いくつものサイトを行ったり来たりしている人もおられると思います。
クリック一つで画面が推移できるようになると、一つの画面を眺め続けるというよりは、ちょくちょく変えて色んなものを遷移していみてしまいます。
自分も読書をするときは何冊かを広げていったり来たりして読んでいたので、自分ながら飽きっぽい性格だなと思っていました。
例えば元マイクロソフトの日本支社長で多読で有名な成毛眞さんも、このような並列読書を勧めていらっしゃるようです。
食べ方に例えると、幕の内弁当をちょっとずつ色々なものを食べていくタイプですね。女性に多いタイプかもしれません。
あちらこちらの情報を遷移しながら考えるという分散思考の価値を、森さんはいわゆる集中力と比較して再評価します。
なぜなら森さんがやってきたような小説を書くとか研究とかをする場合に、新しい発想が必要になってきますが、そのような発想は集中からは生まれないことを経験的に知っているからです。
森さんは研究者だった時に大きな発想を四回程度したそうですが、いずれも集中していた時には思い浮かばなかったといいます。
そして、あとになってから振り返ってみると、とにかく、その問題が解けなくて、あれを試しても失敗、これを試しても駄目という期間を過ごした後、たまたま別のことを始めたり、あるいは国際会議があって、ついでに見学や観光をして戻ってきたあとなどに思いついているのだ。
森さんは別に集中力が必要がないといっているわけではありません。正確には、画期的な発想は集中してモノを考えている時点では生まれてこなかったといってるのです。
集中してモノを考えた後の弛緩した状態、リラックスしていた時にフッと新しい発想が思い浮かんできたといいます。
おそらく、これは僕個人の考えなのですが、思考の強弱、周波数の波が大きい人ほど、新しい突飛な発想が生まれやすいのではないかと思います。
深く潜航して一つのことを思い詰める瞬間と、周りを見渡すようにリラックスしてボーとする時間の落差が大きければ大きいほど、良いアイデアを言うものは浮かんでくるのではないかということです。
つまり新しい画期的なアイデアというものは、物事を深く集中して考える垂直的な思考と、雑多な情報を横断的にみる思考の両方が必要で、その深さと範囲が広ければ広いほど、良いアイデアというものが生まれてくるのではないでしょうか。
それではそのような分散思考はどうやれば良いかと尋ねたくなりますが、森さんはそれには答えられないといいます。
そういったノウハウコレクター的思考こそが、集中思考の典型例だからです。
やる気に依存しない
集中力をだすというのは、意識的にそうするわけですから、要するにやる気を出すことと同義のような気がします。
そしてやる気について森さんはこう言っています。
やる気の問題にしない。やる気なんてどうだって良いから、今日、これだけやろう、ということです。やり始めれば、案外楽しくなるものです。そして、それを続けているうちに、自分が成した仕事量に感動する日が来ます。
このやる気を頼りにしないというのは、以前にも小さな習慣の書評記事で描きました。この本でも、何かを始めるのにモチベーションの力に頼ることほど悪い習慣はないといいます。
モチベーションに頼らずとにかく仕事を始めてみるという習慣、もしくはちょっとした意志の力がやる気を生み出してくれるのです。
と同時に、今度は逆に仕事に精がでてくると、それを意識的にストップさせることも必要になってきます。
このようにやる気と仕事の能率はタイミングが一致しないことが多いのでやっかいなのです。
だからこそ、それをうまく利用しなければなりません。
仕事がのってきたならそのままの勢いでやればいいのではと思いがちですが、そうなると仕事がやる気に左右されることになり、不規則になりがちです。
これは佐々木典士さんの『ぼくたちは習慣で、できている』でも紹介されてるヘミングウェイや村上春樹さんのエピソードと同じですね。
「まずは前に書いた部分を読む。いつも次がどうなるかわかっているところで書くのをやめるから、そこから続きが書ける。そして、まだ元気が残っていて、次がどうなるかわかっているところまで書いてやめる」
やる気は自転車の漕ぐときの負荷と同じようなもので、最初は漕ぎ出しが一番重いようにやる気もでませんが、漕ぎ出して動き出すと徐々にスピードがでて漕ぐのも軽くなっていきます。
そのうち漕がなくてもスピードがだせますが、どこかで止めないとそのままどこまでも行ってしまいます。
そうなると次の日には筋肉痛や疲労で動けなくなってしまうことも考えられます。
なので、どんなに調子が良くても決まった作業量で終えるのが、次の日の仕事に元気かつスムーズに入れるコツなのです。
森さんはやる気やモチベーションは体調に依存しているので、まずは体調を整えることのほうが大事だといいます。
体調は不規則な生活や仕事量で左右されやすいので、やはり一定のところで仕事をセーブすることが大切になってきます。
締め切り前に仕事を終わらせるメリット

締め切り間近にならないと仕事のペースが上がらないという人がいます。
しかしこのような時間の使い方をすると、突発的なアクシデントが起こるとそれに対応ができなくなるリスクがあります。
森さん自身、親御さんが突然亡くなるという不幸があったときも、締め切りのずっと前に仕事を進めていたので、問題なく対処できたといいます。
いずれにしても、毎日書きます。コンピュータのカレンダに、毎日何文字書くと記入して予定を決め、そのとおりに書きます。だいたい前倒しになりますが、決めた予定よりも遅れたことは一度もありません。
編集者の仕事は作家さんの尻を叩くことだと聞いたことがありますが、森さんの担当者はめちゃくちゃ楽でしょうね笑。
自分も夏休みの宿題を最後の1週間で泣きながらやるタイプの子供だったのでわかるのですが、締め切りをプレッシャーにして仕事のやる気を引き起こすやり方は、若い時分の体力があるときじゃないと厳しいような気がします。
さて、そんな森さんですが、正直額面通りに受け取っていいのか迷ってしまうところもあります。
というのは、森さんの仕事の効率は半端ないからです。
小説を書くときに森さんは1時間に約6000字かくといいます。
正確には10分間で1000字ですが、それ以上は疲れるというか厭きてしまうというのですが、とんでもない集中力です。
このブログの記事は短くても3000文字程度はあるのですが、森さんならその気になれば30分程度で書けてしまうわけですからとてもかないません。
おそらく頭の中ですでに書こうとしているストーリーが整理されて、完全に文字として浮かんでいるのではないかと思います。
森さんはたとえて言うなら、高性能のCPUを積んだコンピューターのようなもので、短時間で熱くなってしまうので、しばらく冷まさないとこわれてしまうようなタイプではないかと思います。
一つのことに集中していないというのよりは、分散させながら短時間ごとに集中させているといったほうが正確なような気がします。
ただネットサーフィンして時間をつぶしているのとはちょっと次元が違うところにあるのではないかと思います。
しかしどうでしょうか。将来的にAIが進化していくにつれて、労働の生産性/効率性という指標はそこまで評価されるものでなくなっていくのではないでしょうか。
それよりも、人間だけが持ち得る発想力こそが残された仕事になっていくのかもしれません。
この本は森さんの従来のミステリーのファンの方はもちろん、仕事のやり方や考え方に悩んでいる人にも参考になると思います。