Contents
自分の基礎代謝量を知る
ハリス・ベネディクト方程式(日本版)とは
みなさんは自分の基礎代謝量がいくらか知っていますでしょうか。体重は知っていても、基礎代謝量は知らないという人が多いと思います。
今は基礎代謝量を自動でだしてくれる体重計もありますが、ハリス・ベネディクト方程式から算出してみましょう。
この方程式はもともと欧米人を対象に作られたものであるため、日本人にそのまま当てはめると過大に出やすい傾向があったのですが、それを調整して日本人版の方程式が作られたものです。
具体的な式は以下のようなものです。
男性:基礎代謝量=66.47+13.75×体重+5.0×身長 ー 6.76×年齢
女性:基礎代謝量=65.51+9.56×体重+1.85×身長 ー 4.68×年齢
この式をみればわかるのは、体重と身長があればあるほど基礎代謝量は大きくなり、年齢が高くなると小さくなるということです。
身長は成年になりますとほとんど上下しませんから、変わるのは体重と年齢ということになります。年齢も毎年1才ずつ変わるだけですので、月単位でみると一番基礎代謝量を変動させるのは体重ということになりますね。
体重にかかる係数も身長や年齢の係数と比較して値が大きくなっているので、やはり体重が基礎代謝量に与える一番大きな因子といってもいいと思います。
男性と女性の体重の係数を比較してみると、男性のほうが大きいことがわかります。これは男性のほうがホルモンの関係で体重の増加に対する筋肉量の増加が女性よりも大きいので、代謝量の多い筋肉量の影響が強く出ていると思われます。
それでは具体的に基礎代謝量を計算してみましょう。例として身長175cm、体重80キロの年齢40歳の男性を考えてみましょう。上の式に数値を代入して計算すると、基礎代謝量は1,771kcalとなりました。
もしこれが伸長160cm、体重60キロの年齢30歳の女性であれば、基礎代謝量は795kcalとなります。男性と比較するとおよそ1,000kcal近い差があるということになりますね。
消費カロリーを算出するために使う生活強度について
消費カロリーは基礎代謝に一日の活動量から消費カロリーを加えたものですが、毎日の活動量は平日と休日でちがいますし、スポーツした日と一日寝ていた日ではもちろん違ってきます。
しかし平均して自分の生活強度がどの程度なのかは4分類されており、自分がどれに当てはまるか判断できるはずです。
| 生活活動強度Ⅰ(軽い) | 1.0〜1.1 | |
|---|---|---|
| 生活活動強度Ⅱ(中等度) | デスクワークが主なサラリーマン | 1.2〜1.5 |
| 生活活動強度Ⅲ(やや重い) | 仕事以外にスポーツが趣味 | 1.6〜1.9 |
| 生活活動強度Ⅳ(重い) | ガテン系 | 2.0 |
おそらく家事労働が基本の主婦など、ほとんどの現代人が生活強度Ⅱに当てはまると思います。生活強度Ⅲはサイクリングやジョギングなどを一日一時間ぐらい仕事のほかにやられてる人の強度になります。
自分がどのカテゴリーに当てはまるかを判断して、右側の係数値を基礎代謝量にかけ合わせれば、それがあなたの1日の消費カロリーになります。
上の例でいえば、基礎代謝量1771kcalの男性が生活強度1.2だった場合の消費カロリーは2,125kcalとなります。また女性の生活強度が1.6だった場合の消費カロリーは1,272kcalとなります。
最近はご存知のように1日の活動量を測ってくれるスマートウオッチなどが開発販売されていますので、より正確な数値を知りたい方はそれらを活用して自分の消費カロリーを把握してほしいと思います。
ダイエットにおける摂取カロリーの上限は消費カロリー


さてこれで消費カロリーが把握できたのですが、これが減量の際の摂取カロリーの上限になります。この値を超えてカロリーを摂取すると体重増加につながりますし、それよりも少なければその程度に応じて体重が減っていくことになるわけです。
ただし注意してほしいのは、この消費カロリーの値は結構誤差があるということです。食品であれば、今ではカロリー表示されてるものも多いので、それなりの精度で摂取カロリー量を把握できますが、消費カロリーを正確に測るのはなかなか難しいといえます。
ですのであくまでもこの値は目安としてかんがえてもらって、ダイエットのことを考えると消費カロリーはすこし厳しめに評価したほうがいいと思います。
そしてポイントは運動などで消費カロリーをむやみやたらと増やそうとしないことです。
コントロールすべきは摂取カロリーです。消費カロリーは日々の変動が大きく
体重よりも体脂肪率を重視する


上記のようにハリスベネディクト方程式に年齢、身長、体重を代入して基礎代謝量を計算してもいいのですが、今は基礎代謝量を自動でかつ正確に算出してくれる体組成計が販売されています。
体重計メーカーといえばタニタ食堂でも有名なタニタさんですが、1994年に世界で初めての家庭用の体脂肪計付きヘルスメーターを発売して話題になりました。
それまで体脂肪率を計ろうとしたら、水中にもぐって計るというえらい手間のかかる方法がとられていたのですが、タニタのおかげで乗るだけで良くなったのですね。
体組成計では体脂肪率を0.1%単位で計ってくれますし、やせ、標準、肥満などの判別もしてくれます。お値段もモデルによってはそれほど高いものではないです。
そのためせっかくならということで、最近は体重しか計れない体重計ではなく体組成計・体脂肪計を買う人が増えています。
その精度ですが、時々アスリートやボディビルダーが一般人モードで計って正確じゃないという人がいますが、アスリートやボディビルダーは一般人とはちがう特殊な体型をしているので、アスリートモードで計らないと正確な値がでないのは当然のことです。
ダイエットというとこれまではとにかく体重を落とすことに関心が向いていたと思いますが、大事なのは筋肉を維持しながらいかに体脂肪だけを落としていけるかです。
筋力を維持できればリバウンドのしにくい体質になりますし、何よりも見た目が引き締まってぐっと良くなります。
ダイエットをしたいという人の最終的な目的は、ただ体重の数字を落とすのではなくいかに外見をよくするかということなわけですから、体脂肪率を落とすことに関心を払ってほしいと思います。
日々の体重変動に一喜一憂するのは時間のムダ


体重だけに注目してしまうと、毎日体重計にのってその上下に一喜一憂してしまいがちですが、あまり生産的だとはいえません。
日々の体重変動は摂取した水分量や出ていく汗や尿の量などにも大きく左右されますし、摂取カロリーを減らしたからといって体脂肪がすぐに落ちるわけでもありません。
よくダイエットを始めて数週間スルスルっと体重が落ちていったという人がいますが、それは体脂肪が減ったからではなく、体内の水分の貯蓄量が減ったからです。
特に糖質制限ということで炭水化物の摂取量が減ると、体内に保持する水分量は大きく下がります。”炭水化物”という名前の通り体内で水分を吸収します。
その量は摂取した炭水化物の量の3倍もあるといわれています。
これらの水分は炭水化物を摂取していなければ、尿や汗などで体外に排出されていたものです。
パーソナルジム大手のライザップさんなども水分の摂取を強く勧めている理由の一つは、この糖質制限から来る体内の水分不足を予防するためです。
水分保持量が減ることから来る体重減の効果は初めの数週間だけで、そのあとはいわゆる体重がなかなか減らない停滞期がやってきます。
これは身体が摂取カロリーの低下に反応して吸収効率を上げてくるからです。
これに対応する方法としていわゆるチートデイを設けるという考え方があります。
またこの方法はいわゆる短期限定で目標期日までにかなりの減量を強いられるボディビルダーさんが好んで使われる方法です。ですので一般の方が個人でチートデイを設けてピンポイントに減量をコントロールできるかという疑問もあります。
ひとつまちがえると元の食生活に戻ってしまう可能性もあるからです。
そもそも停滞期は急激な減量に対する身体側の抵抗なので、停滞期を避けるためにも無理なペースでの減量を行わないことが肝心です。
体重を毎日計ってしまうとこの停滞期の段階で挫折してしまうリスクを上げてしまいますし、そもそも計らなければ停滞期の存在にも気が付かないのです。
なので体重を1日単位で計ってもいいのですが、その結果に一喜一憂しないことと、どうせなら週1もしくは月1でもいいと思います。
ある程度の間隔を置いて計るようにしましょう。
体重よりも見た目を重視する


見た目を重視するというのは、ある意味体脂肪率を重視することとほとんど重なってきますが、短期的な数値上の変動に右往左往しないということをいっています。
そもそも筋肉というのはそう短期でつくものではありません。
日本人、特に女性は筋肉が付きすぎることを怖れて、とにかく体重を落とすことだけに関心を持つ人が多いです。
しかし筋肉量を無視したダイエットは、体のシルエットを喪わせてメリハリのない貧相な体つきにしてしまいます。
胸が平板でお尻も小さくて垂れ下がり腰のくびれがなく、筋量がないので姿勢を維持できず顎が出て猫背になり、残念ながら見た目は魅力的にならないのです。
そもそも女性が筋肉をつけるのは思っている以上に大変です。男性とちがって女性ホルモンは筋肉量を増やす方向には働かないからです。
女性が一生懸命筋トレをしても身体が引き締まるだけで筋肥大するようなことはありませんので、安心してワークアウトしてほしいと思います。
筋肉は体積当たりでみると脂肪より20%程度重いのです。つまり同じ重さだと脂肪は筋肉よりも2割程度膨張してしまうわけです。これはとても大きな数字ですよね。
そもそも男性ですら本気になって取り組まない限り、またやり方が正しくない限り簡単には筋肥大しません。女性ならなおさらそうです。
体重を計らないとダイエットが順調に進んでいるのかどうかわからなという人もいると思いますが、身体の変化というのは自分でもみればわかります。
たとえば指の太さです。
指の太さは体脂肪率が減っていくとともに細くなっていきます。それは毎日みても気が付かないかもしれませんが、週単位でみてると確実に気が付きます。
指というのは基本筋肉をつけにくい部分ですから、指が細くなったということは純粋に体脂肪が減った証拠だといえます。
指がまだ太いなと感じたら減量を続ける必要がありますし、大分細くなったと思ったらその時は全身の体脂肪率も相応に減っているはずです。
バフェットはこういっています。
Price is what you pay. Value is what you get.
価格はあなたが支払った金額のこと、価値はあなたが得たもの。
ダイエットに置き換えてみると、体重はあなたが減らした数値のこと、容姿はあなたが得たものということになります。
月平均で体重の3%減をめざそう
ダイエットを始めるにあたり、皆さんは月単位の目標を設定すると思います。月1キロの人もいれば、2か月で10キロという人もいるでしょう。
ボクサーのように2か月後に計量があるとか、結婚式で理想のウェディングドレスを着たいとか何かイベントがあってそれを目標にするとかでなければ、減量の設定にはいくつかの原則があり、それにのっとって目標設定するのが良いと思います。
原則というのはこれまでも繰り返し述べてきた通り、一つは減量を急ぐとリバウンドのリスクが高まるということです。
なのでリバウンドのことを考えると、あまりに性急で過激な目標設定は最初からやめておいたほうがいいということになります。
バフェットは同じく億万長者であるアマゾン創業者のジェフ・ベゾスに対談でこう尋ねられます。
「なぜほかの投資家はあなたの投資手法を真似ないのですか?」
それに対するバフェットの答えが、
Because nobody wants to get rich slow.
なぜって誰もゆっくりと金持ちになりたいとは思わないからね。
ダイエットを過酷にして減量を急げば急ぐほど、失敗のリスクは高まるのです。
次に目標設定をするときに体重~キロというように、絶対値で設定するのが普通だと思いますが、それよりも比率で設定するほうがいいと思います。
同じ10キロやせるといっても、体重が現在50キロの人が10キロ痩せるのと、体重が80キロある人が10キロ痩せるのとでは大違いなわけです。
それよりも例えば月に体重の2%ずつ減らしていこうという目標をたてる。そうすると現在50キロの人なら月1キロになりますし、80キロなら1.6キロになるわけです。
またほかの理由は、体重の減少がすすむと体重は落ちにくくなるからです。毎月3キロというような等間隔での減量だと、体重が減るに従い目標達成が難しくなります。
~%に設定するのかの一つの目安はMaxで3%だと思います。
これ以上に設定すると、ダイエットは過酷になりリバウンドのリスクが高まります。
バフェットはいいます。
“…not doing what we love in the name of greed is very poor management of our lives.”
強欲さは最低のマネージメントだよと。
またもう一つの理由として現在肥満で体調不良の人でも、体重の3%を減らすと血糖値や脂質の血中濃度、血圧、肝機能などの数値が大幅に改善することが医学的に知られているからです。
ダイエットを始めて1カ月で体重3%の減量を達成すると体調がよくなり、体の内部から軽くなったという実感が得られるので、ダイエットに自信を持つことができるのです。
体重計は減量中ではなく減量後に使おう
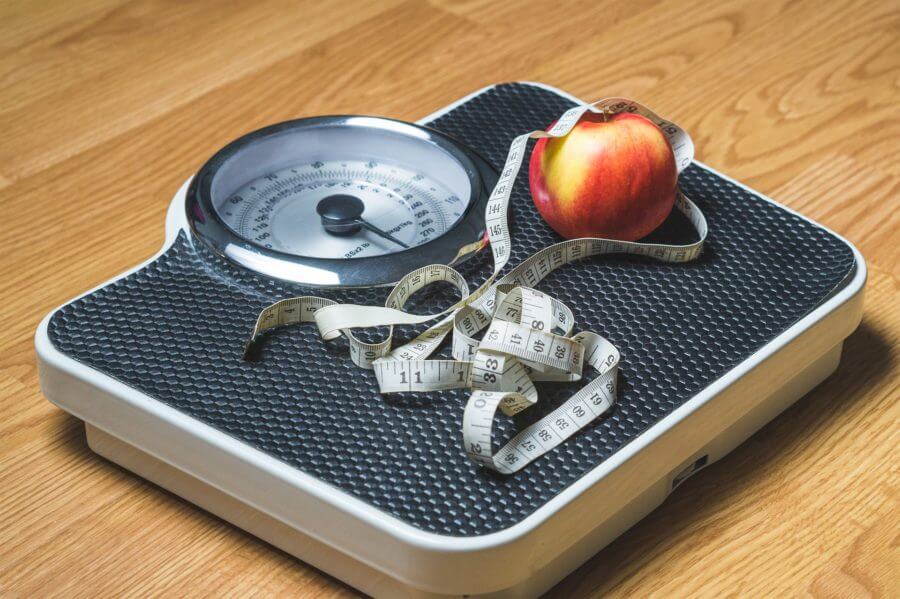
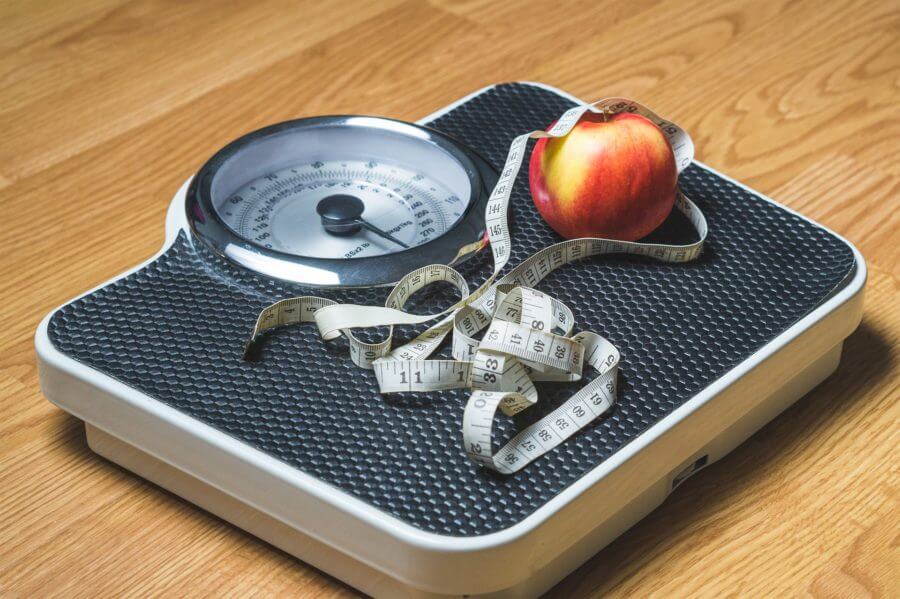
ダイエットしている間は体重計よりも見た目を重視することをお勧めしましたが、体重計がいらないというわけではありません。
体重計が威力を発揮するのは、むしろダイエット終了後の維持期です。
ダイエット後見た目で維持していくのも当然併用していけばいいのですが、細かい数量的な体重の把握はやはり体重計が向いています。
ダイエットが終わって食生活などが正常化していくと、どうしても気が抜けてしまっていつのまにか食べ過ぎていたりしていることがあります。
気が付いたら相当リバウンドしてしまったというようなことがないように、体重計で毎日数量的な把握をするのは効果的です。
ダイエットに成功した暁には、体重計をどんどん活用して体重を維持していってほしいと思います。
バフェットはいっています。
Rule 1: Never lose money. Rule 2: Never forget rule No.1.
1番目のルールはお金を失わないこと、2番目のルールは1番目のルールを忘れないこと。
ダイエットに置き換えれば、1番目のルールは体重を増やさないこと、2番目のルールは1番目のルールを忘れないことになります。
体重が標準体重まで到達したら、あとはそれを維持していくことに関心を払っていくことが、当たり前ですが大切なことなのです。
ハリス・ベネディクト方程式を利用して自分の基礎代謝量を把握しよう
基礎代謝量に生活強度係数をかけ合わせて一日の消費カロリーを把握しよう
計算された消費カロリー量には誤差があるので注意しよう








