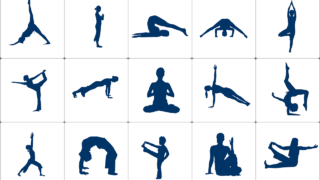Contents
『佐藤可士和の超整理術』佐藤可士和著 日経ビジネス文庫

佐藤可士和さんというと、日本を代表する企業の仕事をいくつも手掛けていることで有名なアートディレクターです。
可士和さん自身を知らなくても、可士和さんが手掛けた仕事は日本で暮らしている限り、おそらくどこかで皆さん目にしたことがあると思います。
例えばTポイントカードのデザイン、ユニクロやセブンイレブンホールディングスのロゴ、キリンの発泡酒「極生」のデザインとか、携帯電話のプロダクトデザインとかもやっておられます。
CMだと、ブラッドピットが出演したホンダインテグラのCMを覚えている方も多いのではないでしょうか。
こうしてみると可士和さんのデザインは、余計な情報をそぎ落としてシンプルで印象的なものが多いですね。
可士和さんのデザインでよく言われることは、今のようなフラットデザインが流行る前からフラットデザインをやっていたということです。
その意味では、時代が彼に追いついてきて、そのままその波に乗って時代をけん引してきたといえるのではないでしょうか。
リアルな世界でもネットの世界でも、広告を含めて情報があふれかえっている中で、人々に広告を訴求するためには、本質だけをポンっと提示することが求められているのだと思います。
さて、そんな売れっ子ディレクターであるはずの可士和さんが、著書のなかで次のような印象的な言葉を述べています。
広告で人々を注目させることは相当難しい
可士和さんは、このことを言葉を何度も変えながら吐露しています。
何日も徹夜し、皆で細かいことまで侃々諤々の議論をしながら作ったものが、ほとんど話題になっていないのです。自分自身、実生活で毎日大量の広告を見ているはずなのに、記憶に残っているものはめったにありませんでした。
広告は見られないもの、を前提にいかに振り向いてもらえるかを考え続ける中で、編み出されたのが、可士和さんの整理術です。
単に情報を整理するというだけにとどまらず、そこからいかに本質的な価値を探り当てるかというノウハウは、汎用性があり、誰にとっても応用が利くという意味でとても貴重なものだと思います。
この本『佐藤可士和の超整理術』は、可士和さんのデザイン創出プログラムのノウハウを余すところなく公開してくれているという点で、とても貴重です。
可士和さんが手がけた初期からの作品、キリン発泡酒「極生」、SMAPの渋谷ハイジャックマーケティング、明治学院大学の学章、国立新美術館のロゴ、ファーストリテイリングのロゴなどの創作過程が掲載されています。
デザイナー自身が赤裸々にその創作意図を語ってくれているという点で、デザイナーのみならず、何かものを創るひとにとってはとても参考になる本だと思います。
空間・情報・思考の順に整理していく

可士和さんは、整理の対象となるドメインを3つに分けて考えています。
3つのドメインとは、空間、情報、思考です。
どのドメインでも考え方は基本同じですが、難易度はこの順で上がっていくといいます。
空間とは、普段我々が暮らしている日常の身の回りのリアルな世界のことです。仕事場の机の周り、ロッカー、カバンの中など、実際の物理的な空間のことです。
空間の整理術の目的は、快適な仕事環境をつくることにあります。
可士和さんの事務所では、スタッフ総出で仕事場の整理に関しては力を入れているのです。
モノを絞って、すっきりと気持ちいい環境の中で、効率的に仕事がしたい。
そのためには整理というものを仕方なしの義務感からではなく、仕事の精度に直結する大事なプロセスとして、積極的な気持ちをもってやらなくてはならないといいます。
これには、仕事上のリスクを最小化したいという思いもあります。
可士和さんがここまで徹底的に部屋の整理にこだわるのは、独立前に勤めていた事務所の部屋がちらかっていて、大事なものが無くなったと思って探し回った経験があったからです。
可士和さんのように、常時複数のプロジェクトを抱えているような事務所で紛失物があると、それだけで大きなリスクになりえます。
可士和さんは身の回りの整理術を究めていく中で、カバンも持たなくなったといいます。
カバンの中身を取り出してそれらを並べて、その頻度の少ない順から省いていく。
そのためには、それぞれの道具のプライオリティを決めていかなくてはなりません。
最終的には、スマホ、家の鍵、カードケース、小銭しか残らなくなり、普段は服のポケットに分散していれているので、カバンはいらなくなったそうです。
とはいえ、ここまで徹底する過程では、不安との闘いでもあったといいます。
だからこそ何を残して、何を捨てるのかの感覚を研ぎ澄まさなければなりません。
情報を整理する
情報ですが、これは画像やテキストなど、実体はないけれども視覚で確認することができるデータのことです。
とにかく、整理のシステムをシンプルにすること!
面白いのは可士和さんは、ファイルの名前の付け方が大事だといいます。
可士和さんが例に挙げているのはユニクロのプロジェクトですが、例えばファイル名を「UNIQLO_001」とするか「UNIQLO_01」で、後々ファイルが増えたら困るのは後者になります。
さらに表記を統一することも大事だといいます。後々検索するときに役立つからです。
とはいえ、このようなルールは試行錯誤してできてきたもので、一朝一夕でできたものではないといいます。
この過程は、試行錯誤の連続です。僕も何年もかかってアップデートし続けてきました。
失敗を繰り返しながら、そのたびに修正を加えていくことで、ルールのアップデートを計っていくというのは、以前記事にもしたMujigramの考え方と似ていますね。
受信メールは、チェックしたらその場で処分することも心がけているそうです。
これは、”とりあえず”との闘いだといいます。とりあえずといって放っておくと、膨大な数になって収拾がつかなくなるからです。
またPC上にも、避難場所となるフリースペースをつくることも大切です。そこに分類しきれないファイルを放り込んでおくのです。
そうすることで、デスクトップ上が格段にすっきりするといいます。
これも、空間の場合と同じ理屈です。忙しいから整理は後回し、ではなく、仕事の効率を上げるために整理をするのです。
情報に視点を持ち込み、ビジョンを探る

広告の仕事というのは、クライアントの意図を読み込みながら、商品の魅力を消費者に効果的に伝えることです。
そのためには関連する情報を整理するわけですが、そこで欠かせないのが自分なりの視点を持ち込むことだといいます。
大切な情報をしっかり見極め、情報同士の因果関係をクリアにしていくことで、進むべき道が見えてくるのです。つまり、情報の整理とは、視点を導入して問題の本質に迫ることで、真の問題解決を行うためのものなのです。
なぜ情報の整理に”視点”が必要になるのかというと、”ビジョン”を見つけるためです。
空間の整理のときもプライオリティをつけることが大切だといいましたが、それには評価軸となる視点が必要なのです。
例えば、先ほど述べましたように、カバンの中身を整理するときはモノを取捨選択しなければなりませんが、その時の評価軸=視点は使う頻度、外での手に入れやすさ、持ち運びの重さ、大きさなどになるでしょう。
それぞれの評価軸で、残すモノ残さないものが変わってくるわけです。それが視点を導入してプライオリティを決めるということです。
視点といっても、もちろん適当に決めることではありません。
自分なりの視点を持たなくてはなりませんが、そのためには時には引いて見つめることも大切だといいます。
本質を探るということは、一見、物事の奥深くに入り込んでいくようなイメージがあるでしょう。でも実は、どんどん引いて離れていくことだと思うんです。客観的に見つめてこそ、いままで気づかなかった真実や大事なエッセンスを発見することができる。
視点を近くにするだけではなく遠くにしたり、焦点をずらしたり、多角的な視点から対象物を観察して本質を浮かび上がらせる。
そのためには物事を客観的に、つまり私(わたくし)から離れてみなければならないといいます。
特に可士和さんの相手にするようなクライアントは大企業が多いですから、色々な組織上のしがらみやパワーバランスなどもあり、バイアスがかかった状況での仕事が多いので、私から離れて物事を客観視するというのは、本質を見極めるという点において大事になってきます。
他人の思考を整理する
そして思考ドメインですが、可士和さんはこの思考の整理が一番難しいといいます。というのも、思考を情報化するというステップが加わるからです。
思考を情報化できれば、あとは情報の整理と同じことをやればいいわけですが、この思考の情報化というものが難しいのです。
というのも他人の頭の中身を整理しなければならないからです。
可士和さんの仕事はクライアントあってのものです。クライアントが売りたい商品のマーケティングを担当するのが可士和さんですから、まずはクライアントの意図を正確に把握する必要があります。
しかし人の頭の中を覗き込めませんから、問診を通して相手の思考を、あの手この手で整理していかなければならないのです。
思考というものは一般的に抽象的なものですから、まずその漠然とした相手の思考を言語化して形にしていかなければなりません。
これが可士和さんの言う思考の情報化です。
もやもやとしていた思いを言葉にすることができれば、筋道を立てて人に伝えることができますから。言語化することで、思考は情報になるのです。
言語化することで、空間の整理の時にカバンの中身を取り出して机の上に並べたように、言葉を並べることで見える化をはかっているわけです。
そのためには、相手のクライアントをお医者さんのように問診していく必要があります。
その際、可士和さんが使うテクニックが、相手に仮説をぶつけることだといいます。
”それってこういうことですか?”と相手の言葉を自分の言葉に置き換えて、相手に尋ねてみる。
その言葉のやり取りのなかで、相手の意図を明確に形にしていくことになります。
可士和さんは仕事を始めたころは、自分のアイデアが枯渇するのはないかと不安に思ったこともあったそうですが、答えは相手の中にあると気づいてからはそういう不安はなくなったそうです。
可士和さんの話を聞いて思い浮かべたのは、夏目漱石の小説「夢十夜」に出てくる一説です。
「よくああ無造作に鑿(ノミ)を使って、思うような眉や花ができるものだな」と自分はあんまり感心したから独言のように言った。するとさっきの若い男が「なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋まっているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだからけっして間違うはずはない」と云った。
ミケランジェロも同じようなこと言ったという話もありますが、可士和さんの「答えは相手の中にある」というのも、同じようなことを指摘しているような気がします。
整理と問題解決は同じベクトルにある
整理というと、仕事の前の準備段階で単調な事務作業だと考えられがちですが、可士和さんによればとても創造的なプロセスの一つだとわかります。
空間、情報、思考というあらゆるドメインにおいて、諸要素をある視点から整理しなおすと、ビジョンが見えてくる。
ビジョンというのは、可士和さんの言葉によれば、”あるべき姿”です。
あるべき姿というものは、整理することから見つけることができるのです。
アートディレクターというと、創造的な仕事だと思われがちですが、クライアントがいて、クライアントの意向を取り込みながら、商品を世間に訴求していくわけですから、ディレクターが自分勝手な広告をつくられると、困ってしまうわけです。
芸術がゼロから新しいものを創造するプロセスだとしたら、広告業界におけるアートディレクターの仕事は、クライアントもしくは商品と消費者をつ媒介するデザインをつくることです。
すなわちコミュニケーションデザインです。
このコミュニケーションデザインという言葉は、可士和さんも大学にいたころに、何度も先生から聞かされた言葉だったそうですが、耳で聞かされても頭には入ってこなかったそうです。
コミュニケーションデザインであることを忘れると、独りよがりのデザインになり、どうしても表層的なものになりがちです。
一見刺激的なデザインは、消費者に訴求されるような気がしますが、一瞬目を引くだけで、持続力がないといいます。
たとえるなら、子どもが隠れていた物陰から出てきて、「わっ!」と驚かせるようなもの。驚かせたほうは、怒ったり相手にしなかったりするかもしれません。相手の理解を得たり興味をひいたりしないと、本当に心を捉えたことにはならないのです。
アートディレクターの仕事とは、クライアントと対話して、商品の本質的価値を浮かび上がらせて、それを世間にデザインでコミュニケートさせないといけないので、芸術家がゼロから表現することとはまた次元が違う行為になります。
そのためには、まずカバンの中から、PCから、クライアントの頭の中まで、整理することから始めなくてはなりません。
可士和さんにとっては、世間に訴求するデザインをつくることと、机の周りを片付けること、パソコンの画面を整理することは同一線上にあります。
モノや情報や思考を整理して、プライオリティをつけて並べ替えて、内にあるビジョンを見出すという一連の過程は、どのドメインでも応用がきくからです。
整理は、新しいアイデアを開く扉です。
この本は、可士和さんの最初の著作であり、初期から中期にかけての可士和さんの数々の仕事について種明かしをしてくれている貴重なものです。
また、本書とも関係するテーマである仕事上の「打ち合わせ」についての本もだされていますので、こちらも関心を持たれた方はどうぞ。