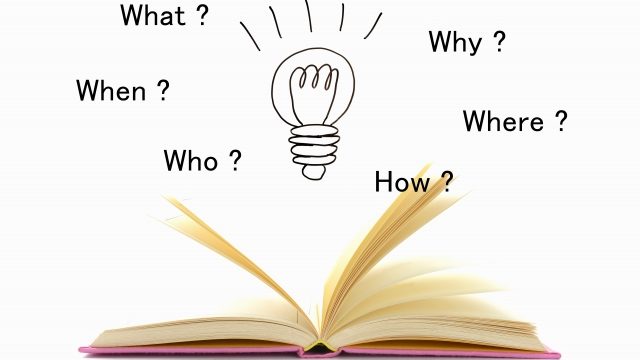『人生が整う家事の習慣』本間朝子 藤原千秋 河野真希監修 西東社

家事を苦手だと感じている方は多いと思います。
自分もその一人ですが、なぜ家事を苦手と感じるかというと達成感がいまいち得られにくい、やってもやっても終わらないという気がするということがあると思います。
家事というのはやりこめばいくらでもやれるし、ほどほどにしても格好をつけることはできます。誰かに管理されてやってるわけではないので、その達成度は自分で決めなくてはいけないのです。
他の仕事のようにここまで仕上げなければならないというものでもないので、そこの塩梅が難しいのです。
この『人生が整う家事の習慣』は、「私の家事、本当にこれでいいのかな?」といつももやもやしている人に贈る本です。
家事には100人の家庭があれば、100通りの方法があり、どれが正解というわけではないといいます。
それぞれの家庭に、それぞれの価値観があるように、家事の在り方も、違っていいはずです。
一度、自分の家事の現実と理想を見直してみましょう。基準は「自分と家族」です。家事の正解は、自分で決めていいのです。
家事の現実と理想をどう把握するかが家事をうまく効率的にこなす秘訣になるといいます。
そのためにはまず家事の見える化をすすめなくてはいけません。
家事の見える化をすすめる
なんでもそうですが、成果の見えにくい仕事はなんだかもやもやしてすっきりしません。家事はその成果の見えにくい仕事の一つです。
これが多くの人にとって家事が苦手だと感じられる理由の一つになっています。
なのでそのような消化不良の気分を打ち消すためにも、家事の見える化を勧めてみましょう。
そこで本書が提案するのが、以下の家事の見える化4つのポイントです。
- 家事の棚卸をすすめよう
- 家事の時間割を見直そう
- 家事のリスト化をすすめよう
- リストを活用しよう
家事の棚卸とは、毎日やるべき家事それぞれについて、現状どれくらいできているのか、どれくらいの時間がかかっているのかについて書き出してみます。
これは結構大変なことですが、一度やってしまえば2度とやらないで済むので頑張ってやってみましょう。
そしてそれぞれのタスクについて自分の理想の状態をイメージし、現実の達成度がどの程度なのかを数値で評価してみましょう。
評価の低いタスクについてその原因を考えてみましょう。苦手だ、面倒だ、やり方がわからないなど色々出てくると思います。
原因がわかればその対処法を考えてみましょう。
家事の時間割を見直すというのは、自分がどのような時間帯や時間配分なら最も効率的に家事が行えるのかどうかを把握して見直すというコトになります。
自分が朝型なら早めに起きて掃除をするとか、夜型なら夜にやれる家事をその時間帯に放り込むとか、自分がどちらの時間帯なら動けるのかを考えてみましょう。
家事には気合を入れないとできない家事と、何か他のことをしながらでもできる気楽な家事の二つがあります。
気合を入れないといけない家事を動ける時間帯に廻しましょう。
ポイントは、タイミングと区切りをはっきりさせるということです。例え終わらなくても~時までにと決めたらその時間で終わらせることが大切です。
家事のリスト化というのは、主に毎日やらなくてもよい家事をリスト化するということです。そのような家事は後でやろうとして結局おっくうになりがちです。
リスト化して活用することによって、やるべき家事を忘れないようになります。
自分は「HABIT BOOK」アプリを使って毎日はやらない家事習慣を管理しています。
こちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。
家事の習慣化をすすめる
家事というのは学校で丁寧に習うものではないので、基本的には親御さんから学んだり、見様見真似で要は自己流でやってしまいがちです。
自己流の方法で家事を続けていると気が付かないまま非効率な方法でやってしまい、またそのことにも気が付きません。結果、かけている労力と時間に見合わない成果になりがちで、そのままだと家事のことが嫌いになってしまうでしょう。
なのでいつもの家事のやり方や時間配分を意識的に見直してみましょう。
そして新しい効率的な方法を試してみて、これは続ける価値があるなと感じたら、その方法を習慣化させていきましょう。
そのためには、例えば掃除なら毎日ちょこちょこやるのが一番楽で習慣化しやすいのです。
というのも汚れは最初のうちに落としてしまうのが一番楽ですし、一分以内ですんでしまうようなちょこちょこ掃除を習慣化することで、掃除の効率性がグッとあがります。
また良く汚れるような場所にそれに適した掃除道具を揃えておくことも、ちょこちょこ掃除をしやすくするコツです。
良く汚れるような代表的な場所は、バス、キッチンやトイレなどです。浴室では洗剤・ブラシ・スポンジはつるして収納しておきましょう。
サッと取れる場所に道具があれば掃除するのが億劫にならないですみます。そのためには使いやすいハンディタイプの道具や使い捨て可能なものを選ぶのがコツです。
掃除を習慣化するには、例えば一日5分の片づけタイムをもうけるというのも有効です。この5分という時間設定がキーポイントになります。
つまり時間を区切ることで、掃除の成果をどれだけクリーンにしたのかではなくその時間内でどれだけ掃除をしたのかどうかに求めるということです。
掃除が億劫になるのはどこまでやれば終わるのかというのが見えにくという点にあるわけですから、こうやって5分と時間を区切ってやることでストレスなく掃除に取り掛かれます。
1日5分だと1週間で35分なわけですから、週末に30分掃除をするよりも、一日5分のちょこちょこ掃除を習慣化させるほうが長続きすると思いますし、部屋も恒常的にきれいになるでしょう。
1日5分のちょこちょこ掃除タイムをどの時間帯にするのか前もって決めておきましょう。出かける前、食事の前、寝る前、朝食前などです。
モノをそもそも増やさない
掃除を効率的にかつ時短ですますには、そもそも家の中のモノを増やさないことをこころがけましょう。
そのためにモノを一つ買うときは、一つ処分してから買いましょう。モノの出入りをプラマイゼロにするということです。
これなら、「今持っているものを処分してでも、これが欲しいか」と自問することが癖になります。そうなると、不要な衝動買いも抑えられます。
衝動買いを抑えるには、例えばネットで購入するときにも、まず狙いの商品をひとまずお気に入り登録してすぐに買わないようにすることです。
一息いれてもまだ欲しいと思えるのなら買ってもよいと思います。
それでは既存のものを整理するにはどうしたよいでしょうか。
- 全部出して眺める
- 分類する
- 4つに分ける
まず整理する範囲にあるものを全部一気に出して床に並べてみましょう。そしてそれらをしばらく眺めてみましょう。
次にアイテムごとにまとめてみましょう。例えば衣類ならTシャツはTシャツで、長袖なら長袖で、セーターならセーターでという風に。
まとめてみるとそれぞれのアイテムの偏りが見えてくるはずです。
最後に4つに分けるですが、4つとは必要、不要、迷う、移動のことです。
衣類でいえば、必要ならそのまま元の場所に戻す。不要なら処分します。迷ったものはボックスへ。移動なら他の場所に移すということになります。
ボックスにいれたものはしばらくはそのまま保持して、またどうするか考えましょう。
家事のしやすい家づくりと部屋づくり
本多さおりさんの記事でも指摘しましたが、家事を効率的かつ億劫にならずにやる一番の方法は、そもそも家事がしやすいおうちづくり、へやづくりをすることが大切です。
本書では家事がしやすい家のポイントを7つ挙げてくれています。
- 生活動線の途中で家事ができる
- 家事動線が短い
- モノが少ない
- 掃除しやすいレイアウト
- 汚れが少ない工夫がある
- 使う場所に収納してある
- ひと目でわかる形で管理
1番2番6番のポイントは基本的に同じことを言っています。
たとえばその場所を掃除するのにいちいち掃除機を他からとってこなくてはいけなくなるというのは掃除を億劫にさせる原因になります。
生活動線の途中で家事ができ、家事動線を短くできれば、自然と掃除の頻度も増えていきます。
そのためには使う場所に道具類を収納しておかなければなりません。
4番目のポイントですが家具のレイアウトも大事です。家具のレイアウトは心地よさを重視して決める方が多いと思いますが、掃除のしやすさも大事な要素です。
「引っ越してから一度も変えていない」ということであれば、一度家具の配置を見直してみましょう。
家具によって「行き止まり動線」になっているところを「回遊動線」に変えてあげるだけで、掃除の効率性は飛躍的にアップします。
例えば家具と壁の隙間をモップが入れるような長さを空けるとか、
7番のわかる形で管理するというのは、家事をする際に考えずに動けるようにするということです。
考えずに動けるというのは、いつも決められた手順とルートで掃除ができるということです。
掃除をするのにゼロから手順を考えたり、ルートも毎回変わってしまうとそれだけ時間がかかり、成果もまちまちになります。
この本は掃除だけではなく、洗濯や収納から食事の準備までかなり細かいところまでノウハウを紹介してくれていますので、一通り目を通せば役に立ってくれるノウハウ本だと思います。