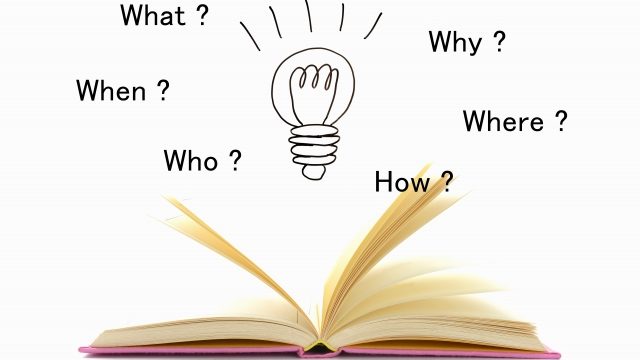『家事がしやすい部屋づくり』本田さおり著 マイナビ

家事といってもたくさんありますよね。掃除、洗濯、炊事、そのほか、育児、買い物、ペットのお世話・・・etc。
それぞれ種目が違いますし、それぞれの得手不得手もあると思います。
一言で家事が苦手だといっても、人それぞれの事情があるわけです。
家事というのは手を抜けば、ある意味いくらでも手が抜けます。だけれども、やはり幸せな毎日を送るためには、手を抜くのは簡単ではないなと考える人がほとんどだと思います。
この匙加減の難しさが、家事を苦手だと考える原因の一つだと思います。
この本『家事がしやすい部屋づくり』の著者本多さおりさんは、整理収納コンサルタントとして日々、お客さんの家事のコンサルティングをされています。
多くのお客さんの事例を客観的に見てきた中で、本多さんは家事がうまくいかない原因をまずは収納に求めています。
じつは家事のイライラは、収納に原因があることも多いのです。
家事がはかどるには、家事がしやすい部屋づくり、家づくりが必要になるわけですが、そのためにはやはり収納の工夫が大切になります。
家事というのは”繰り返し”が大部分を占めます。この繰り返しルーティンをいかに効率よくこなしていけるのかが、夢のズボラ家事実現への近道になります。
そのためには、毎日のちょっとした気づき、本多さんの言葉でいえば、”少しの見直し”をしてあげることで、ずいぶんと家事が楽になります。
ズボラだからこそ、日々、家事をアップデートさせよう

特に女性にとって、日々暮らす空間を快適にしつらえたいと思うのは当たり前だと思います。
そのためには家事を勘張りたいと思う自分と、面倒だなと思う自分、大体二人の自分がいて頭の中で相克しあっています。
その二人の欲求を解決してくれるのが、本多さんが薦めるズボラ家事です。
ズボラ家事というのは、本多さんの言葉でいえば、家事を少しでもラクにこなせる仕組みのことです。
面倒だからどうするか? を起点に家事の方法を考えれば、とっかかりの億劫さは、かなり解消されるのではないでしょうか。
本多さんは家事の仕組みは単純明快であること、先回りして作っておくことが大切だといいます。
そしてプロとして活動されている今でも、試行錯誤の毎日だといいます。
それでは本多家の家事メソッドの一部をここでも紹介しておきます。
- 家事に必要な道具がとりやすい
- 繰り返しの面倒をほおっておかない
- モノの定位置が明確である
- 風の通り道がある
- あとラク家事を組み込もう
- 自分に合った方法を採用する
掃除機や雑巾がけなど、どんな家事にも道具は必要になります。なのですぐに取り出して使えるような形で置いておかなければなりません。
特にほぼ毎日使うような道具類は優先的に便利な場所に置いておきましょう。
「深い引き出しから、フライパンをとろうとすると、ガチャガチャ干渉してしまう」など、取り出そうとするたびにストレスを感じていませんか。
感じるなら、そのストレスの元を意識して対応する必要があります。
部屋やキッチンが片付かずにすぐにちらかってしまうのは、モノの位置が決まっておらず、毎回探さなくてはいけなくなるからです。
なので、毎回定位置に片づけるようにして、また家族にもわかるようにラベリングをしておきましょう。
また使用頻度や用途別にグルーピングしておくことも大切です。
本多さんは団地に引っ越してから気が付いたそうですが、風の通り道を部屋に作っておくと、部屋の”よどみ”をを解消してくれるそうです。
家に流れる”気”をよくするためにも、朝起きたら窓を開けましょう。
また一日の家事労働を10とすれば、そのうちの1は明日のための家事貯蓄に廻しておけばいいといいます。
家事貯蓄とは、少し先の自分が少しでも楽できるようなひと手間のことです。これがあとですこし家事がラクになる、あとラク家事です。
また、家事の方法に誰にでも通用する絶対的な方法はないといいます。
なので自分に合った方法を取捨選択して、自分で自分の家事の方法を見つけていってほしいといいます。
めぐりのよいキッチンは時短家事のかなめ

本多さんが理想とするキッチンの在り方は、”めぐりのよい”キッチンだといいます。
キッチンは料理や洗い物をするために、毎回様々なものが運び込まれて出ていくところです。
なので、色んなものがめぐりやすい状態にあるキッチンを、めぐりのよいキッチンと呼ぶのです。
体のめぐりがよいひとが健康でいられるように、めぐりのよいキッチンは、健全な暮らしになくてはならないと思っています。
そして、
めぐりのよいキッチンとは、ものを使いやすくするための土台=収納が整っていて、ひとが動きやすく、家事がしやすいキッチン。
めぐりのよいキッチンをつくるためには、いくつかの工夫があります。
まず鍋やフライパンなどは働き者に限るということ。
どんな道具も使われないのはかわいそうなことですし、できれば毎日休むことなく働いてくれる道具をそろえたいものです。
本多さんのキッチンの作業台は、まな板2枚分の狭いスペース。
そんなスペースで窮屈な思いをして動かなくてよいように工夫をしています。
まず作業台のトップは、いつも何もない状態にしておくことです。
作業台にいていいのは、今動いているものだけ。それ以外はほかの別の場所によけるシステムを作っておきましょう。
本多さんは、キッチンに関していえば、収納量より作業スペースのほうが大事だといいます。
カウンターが長ければ、色々家電も置けますし、複数の人と作業ができるようにもなります。
家事動線を意識する
この本の最後に建築家の伊藤裕子さんとの対談が載っています。
そこで伊藤さんが設計にかかわった家について語られています。
本多さんが、伊藤さんが設計された家を評価するのは、もちろん、”家事がしやすい家”だからです。
伊藤さんによれば、設計の時に気を付けているのは女性目線です。それはつまり家事動線が考えられている設計でなければならないということです。
家事動線といえば、女性はやることが多くていつも忙しいし、基本、面倒くさがりでしょう? だからまず、どんな行動でもなるべく少ないアクションでできることを考えて設計しています。
本多さんは、取り出すステップをなるべき省きたいので、収納は基本、オープン収納を心がけています。
オープン収納なら、パッと見て何がそこにあるのかがわかって、サッと取り出せるからです。
伊藤さんが家事動線と同じく意識しているのは、回遊動線です。
回遊動線とは、伊藤さんの言葉でいえば、家の中をぐるぐるとひと筆書きのように回れることです。
ひと筆書きのように掃除機をかければ、一周ですむわけですからね。
言い換えると、全部の家事が最短距離ですませられるように、行ったり来たりを最小限にする回遊可能な間取りが良いのです。
この本は、本多さん家族が住む決して広いとはいえない間取りのなかで、本多さん自身が日々取り入れている工夫やノウハウが開陳されています。
本多さんの実体験に基づいているので説得力がありますし、片づけの専門家として様々なお宅を拝見してきたことからの客観的な目線のするどさがあります。
本多さんは何冊かの著書をだされていますが、最近のなら「とことん収納」が良いと思います。