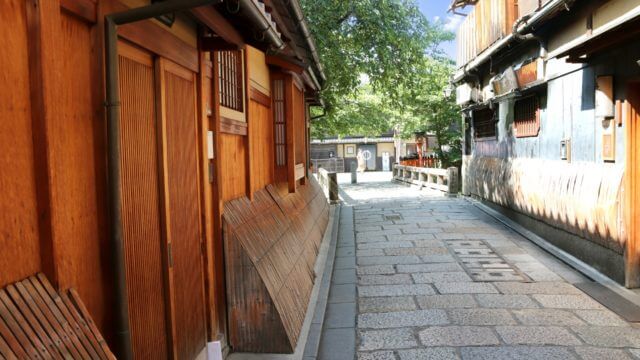Contents
「極上の一杯」の淹れ方がわかる!美味しい珈琲のある生活 堀口俊英著 PHPビジュアル実用BOOKS

今回のレビューは堀口珈琲の創業者が書いた「極上の一杯の淹れ方がわかる!美味しい珈琲のある生活」(画像をクリックするとアマゾンに飛びます)です。
美味しいコーヒーって何ですかといわれると人によって答えは様々だと思います。
朝起きての一杯がとにかく一番という人もいるでしょうし、行きつけのカフェで飲むカプチーノが好きだという人もおられると思います。
ここでは業界の第一人者で堀口珈琲の創業者でもある堀口俊英氏の言葉を紹介したいと思います。
ここ数年でたどり着いた結論は「美味しい珈琲は果物のようだ」ということ
コーヒーはコーヒーであって果物じゃないと思われる人もいるかもしれませんが、堀口さんによれば、良い土壌のなかで栽培者によって熱心に作られたコーヒーには確かに果物のような香味がするといいます。
実際、珈琲はアカネ科の常緑樹で赤い実をつけます。それがチェリーに似ているので、「珈琲チェリー」といわれているのです。
珈琲のおいしさはどこで決まる?

そもそも珈琲のおいしさはどこで決まるのでしょうか。
それはまず第一に生豆の品質で決まります。
もちろん焙煎や抽出などもおいしさに関係してきますが、まずなによりも生豆の質が良くなければ、焙煎や抽出で挽回するのは難しくなります。
これは普通の食材でもいえることですよね。調理や料理の仕方である程度はおいしくできますが、魚自体の鮮度がないと魚料理はおいしくなりません。
珈琲を飲むには生豆→焙煎→抽出の工程を経るわけですが、この生豆/焙煎/抽出のおいしさの比率は6:3:1、もしくはそれ以上に生豆の割合が高いという人もいます。
それぐらい昨今はコーヒー業界において生豆の品質が重視されるようになってきたということでしょう。
それではその生豆の品質はどのように決まるのでしょうか。以下の格付けが重要になってきます。
- 標高による格付け
- スクリーンサイズによる格付け
- 欠点数による格付け
標高が品質に関係してくるのは標高が高いほど気温の寒暖差が激しく、それが豆の酸味をうみ出すからです。
そして豆の酸味はロースト次第で甘みに変化して豊かな香味を生み出すのです。
コーヒーの樹木には大小さまざまな果実がついているのですが、大きい果実のほうが欠損率が低くまた見栄えもいいので高く評価されるのです。
最後に欠点数による評価ですが、多くは三〇〇グラム中に含まれる欠損豆の数にしたがって評価されます。
欠損豆は嫌な香味やかびた匂いを発生させるので、これらが多く含まれているような豆は評価が下がるのです。
良い珈琲豆とはなにか
それでは良い珈琲豆にはどんな特徴があるのでしょうか。
堀口さんによればその特徴は次の4つです。
- 新鮮であるほうが良い
- 焙煎してから日が浅いほうが良い
- 外見がきれいなほうが良い
- 香味がきれいなほうが良い
珈琲豆が食材である限り、当然ながら新鮮であるほうが良いわけです。
発酵食品であればまた話は違ってきますが、食材である限り商品となった瞬間から腐敗=酸化が始まります。
珈琲豆の場合は酸化すると嫌なにおいや酸味に変化していきます。ひどい場合にはお腹の具合がおかしくなったりします。
珈琲に苦手意識を持つ方の中には、たまたま珈琲体験の初期に品質の悪い珈琲を飲んでしまって、その時の嫌な感じが残ってしまっているので、それ以来飲まず嫌いになってしまっている人もいます。
なので一度は苦手意識を持たれた方も、しっかりとした品質のコーヒー豆で淹れたコーヒーを飲む機会を作ってほしいと思います。
焙煎してから日が浅いほうがいいというのも同じ理由ですね。
焙煎すると生豆から乾物に変わるので、そこまで鮮度にこだわる必要はないのではないかという人もいますが、焙煎するからといって豆から水分が完全に抜けるわけではありません。
一般に生豆には水分が12%程度含まれていますが、焙煎をすると3%程度になります。
焙煎しても酸化は止まりませんので、できるだけ早いうちに召し上がるのが正解です。
外見がきれいなほうが良いというのは、焙煎して色がついても色ムラがなく、きれいなものが高品質な豆になります。
最後に香味がきれいなほうがよいのは、欠点豆が混入してると珈琲液が濁り味も濁ります。飲んだ時に強い酸味や嫌な臭いがなく、きれいな香味がでていれば高い品質の豆だといえます。
良い珈琲豆の選び方

それでは実際に良い珈琲豆を購入する際の判断基準はどこにあるのでしょうか。
堀口さんによればそれは、
- 生産国、生産地域、農園、品種、精製などが表示されている
- ローストの度合いが表示されている
- 豆と粉であれば豆のままのほうがベター
- すんだきれいな味わいがする
- 時間がたっても美味しさが衰えない
一般的には高品質な豆ほど関連情報がしっかりと記載されています。
生産国、地域、農園、品種、精製にわたるまでしっかりと記載されているものは、豆のトレーサビリティが確保されているということなので、当然評価が高くなります。
産地が自分の名前を強く押し出すのは、自分の豆の品質に自信を持っている証拠だからです。
粉にするとその瞬間から空気に触れる面積が増えてしまうので、豆よりも酸化のスピードが上がってしまいます。なので豆のままのほうがベターなのですが、粉でも家の冷凍庫にいれて保存しておけば、酸化を止めることが可能です。
良い豆は香味がきれいで嫌な味がしません。また時間がたっても美味しくいただけます。
新鮮な豆はドリップでいれたときにローストにもよりますが、一般的には新鮮な豆ほど二酸化炭素を多く含んでいるため、粉がドリッパーのなかで膨らみます。
ドリッブしたときに粉が大きく膨らんできたら、それは新鮮度を計る一つの目安になります。
新しい珈琲の潮流
2000年ごろから珈琲の流通の世界も変わってきました。
珈琲の履歴を表示して、産地ごと農園ごとの品質を消費者にわかるようにしようという流れです。
堀口さんの言葉によれば、
「もっとおいしい珈琲はないの?」と香味が追及された結果、「どこの地域で、誰が、どんな品種を、どうやって栽培したのか?」などの情報に基づいた珈琲が求められるようになりました。
そしてアメリカのコーヒー協会が新たに「スペシャリティ珈琲」という概念を誕生させて、従来の珈琲と区別するようになったのです。
スペシャリティ珈琲とは、味を評価するカッピングスコアで80点以上という高評価の豆に与えられる最高級のコーヒー豆の称号です。
堀口さんの定義によれば、「珈琲のカップに至るまでの工程で、ベストが尽くされたものに与えられる称号」ということになります。
スペシャリティのほかには、プレミアム珈琲、コマーシャル珈琲、そしてローグレード珈琲があります。
このように豆の由来を消費者にはっきりさせて品質を格付けする。
そして生産者である農園主の豆を買いたたくのではなく品質ごとに評価してフェアトレードで購入する。
そのうえで消費者に商品を届けるという一連の流れを珈琲界のサードウェイブと呼んでいます。
堀口珈琲も日本でその流れをけん引してきたお店のひとつになります。
珈琲豆のローストの分類

珈琲豆のローストの度合いはまずは大きく浅煎り、中煎り、深煎りに分けられます。
浅煎りはライトローストとシナモンローストに分けられますが、実際のところライトローストはほとんど利用することはありません。
シナモンローストも酸味が強く残っているので、そこまで酸味が好きじゃない限り個人が選ぶ回数は少ないと思います。
中煎りはミディアムローストとハイローストに分類されます。
ミディアムは酸味が強く感じられて、ブルーマウンテンなど20年前に主流だったものです。
ハイローストは酸味とコクのバランスが取れていて最近の主流でもあります。
深煎りはシティロースト、フルシティロースト、フレンチロースト、イタリアンローストに分類されます。
シティローストはやや深煎りで酸味としっかりとしたコクがあります。最近の主流の一つです。
フルシティローストもやや深煎りで、少し苦みが出て酸味がかすかに感じられます。しっかりした味わいです。
フレンチローストはしっかりとした苦みで、カフェオレやアイスコーヒーなどに合います。
イタリアンローストは少し焦げたような味わいがします。見た目は黒くてかなりしっかりとした苦みが出ます。
イタリアンローストなど超深煎りでだすところは、こだわりのネルドリップで抽出するお店が多いと思います。
とはいっても日本人はやっぱり深煎りが好き!?

堀口さんは確かに日本のサードウェイブを引っ張ってきた一人なのですが、現在のマーケティング主導のトレンドが入ってくる前から日本で独自に豆の品質と卸を開拓されてきた方です。
なので表面的な流行に捉われないしっかりとした考えを持っています。
その一つが日本で伝統的に好まれてきた深煎りの再評価です。
いわゆるサードウェイブというと浅煎りの焙煎が好まれていて、浅煎りこそが良質で新鮮な豆を生かす唯一の方法だという考え方がありますが、堀口さんはそこに疑問を感じることがあるといいます。
上のチャートは焙煎度合いと香味の違いで分布させた堀口珈琲が販売する豆の種類です。
横軸はローストの程度を表していて、左から右に行くと浅煎りから深煎りになります。
縦軸はフラワー、フルーツ、ハーブ、ナッツ、キャラメル、チョコレートなど香味の違いを表しています。
1番から9番まで番号順に浅煎りから深煎りになっていることがわかります。
基本的には浅煎りのほうが左下、深煎りのものが右上と、左下から右上へと対角線上に商品が並んでいます。
これは浅煎りのほうが果実の香味を、深煎りのほうがチョコレートっぽい香味をだしてくるからですね。
なので6とか8のような深い焙煎にもかかわらず果実っぽい香味をだしてくるというのは珍しい豆だと思います。
分布をみるも商品が特に浅煎りに偏っているということはありません。浅いものから深いものまでバランスよく並んでいます。
ただし一番の浅煎りでもミディアムハイとハイローストの中間で、それ以外はハイロースト以上です。
堀口さんはあまりミディアム以下の商品は扱いたくないといいます。
一番深いイタリアンローストが二種類あり、むしろ深煎りのほうに重点が置かれているように思います。
堀口さんは元々深い焙煎でもえぐみや焦げ味のない味が出せると考えていたそうですが、昔はなかなかそのような焙煎に耐えられるような豆が入ってこなかったそうです。
今はそのようなポテンシャルを持った豆が入ってくるようになったので、商品として揃えられるようになったといいます。
堀口さんによれば、人の好みは浅煎りからはいっても最終的に深煎りに流れるという考えがあります。
サードウェイブで浅煎りこそが主流みたいな考えが世界的に流行りましたが、その揺り戻しが来ているといいます。
珈琲の美味しい淹れ方:ドリップ編
堀口さんが考える淹れ方の評価の基準について紹介しておきたいと思います。
淹れ方にはドリップのほかにフレンチプレスやネルドリップ、水出しなどがありますが、ここでは抽出の基本であるドリップについて紹介します。
10回抽出して10回同じような香味にできること。一人分と四人分を抽出した時に同じ香味にできることが、これが基本的なスキルとなります。
お店ではスタッフ間で淹れ方が微妙に変わってきますが、これを統一できるように練習するそうです。
僕も何百回といれていますが、毎回同じ香味にできているかというと自信がありません。
ただ毎回メモリーを使って数値を計って淹れています。一人分、二人分のコーヒー豆の量、抽出量、抽出時間をできるだけ一定になるように調整します。
メモリーを使う理由は、抽出条件を一定にしない限り味の変化を評価することができないからです。
これは堀口さんも実践されている習慣で、抽出条件を一定にしない限りお店でだされている味の評価ができないといいます。
なのでどんなに抽出に慣れてきたとしても、毎回しっかり計りながら淹れてみましょう。
そうすれば自分が買ってきた豆の評価が正確になりますし、自分の好みの味の豆を探し出しやすくなります。
淹れ方の基準
| 粉の量 | 抽出量 | 抽出時間 | |
| 一人分 | 10~15g | 120cc | 2~3分 |
| 二人分 | 20~25g | 240cc | 2~5分 |
| 三人分 | 30~35g | 360cc | 3~5分 |
| 四人分 | 40~45g | 480cc | 4~5分 |
堀口珈琲での基準は上の表のようになっています。
自分はもう少し抽出量は多いです笑。大体二人分で300ccです。
そして一人分を淹れることはあまりありません。
一人分は粉量が少ないため抽出が難しく、二人分の粉量がないとうまく抽出できないからです。
そのため自分が飲む場合は二杯目は後で飲むことになりますが、良質な豆は味が落ちないので安心して二杯分淹れられるのです。
堀口珈琲はスイーツもおいしい

この本を手に取ると、半分くらいは珈琲と一緒に嗜むスイーツ類が紹介されています。
実際堀口の店舗にいくと珈琲はもちろんのことスイーツ類もおいしいです。
いわゆるケーキ専門店のケーキ類とは若干違うのですが、素朴なのに上品な味です。
これは堀口氏が珈琲との食べ合わせ飲み合わせを重視しているからだと思います。
堀口さんの不思議なところは珈琲の味と品質を追求しながら、一方で珈琲の食としての可能性について柔軟だということです。
なのでこの本にはアレンジ珈琲のサンプルもたくさん出てきます。
これは堀口さんの意識の中に珈琲はほかの飲食物と競争しているという考えがあるからではないでしょうか。
珈琲単独では生き残れないという危機感から、いかにして珈琲の可能性と多様性を消費者に知ってもらうかという強い信念があるのだと思います。
堀口系列のコーヒーは東京以外でも飲めます
コーヒー業界のメジャーなブランドといわれるとたとえばドトールだとかUCCだとかスターバックスを思い浮かべるかもしれません。
サードウェイブならブルーボトルなども特にネット上では認知度は高いと思います。
これらのブランドは一般消費者への認知度はずば抜けています。
しかしもうひとつ、一般消費者にはさほど知られていないけれども、珈琲店を経営している個人店の店主さんや開業を夢見るセミプロの人にはもちろんのこと、珈琲フリークさんなどには良く知られているブランドがあります。
それが堀口珈琲や丸山珈琲やカフェバッハなどです。
いずれも関東にあるお店で、堀口は小田急沿線、丸山は軽井沢発、カフェバッハは南千住にお店があります。
ほかにも名店といわれる個人店はたくさんあるのですが、これらの店を特徴づけるのは、弟子筋が全国に店を開いているとか、豆の卸を通じて地方でも飲むことができるというところです。
例えば堀口系列の大阪のお店というと、玉造のHiromi Fujita Coffeeや堺のDear Cupです。
バッハ系列で大阪のお店というと、野田阪神や阪急梅田駅地下三番街にあるカフェバーンホーフ、高槻にあるリザルブ珈琲店です。
京都まで足を延ばせば今出川にカフェデコラソンがあります。
丸山は系列店がそこまで地方にあるというわけではないのですが、大阪なら高島屋難波店にある家具屋メゾンドファミーユに併設されているカフェでは丸山の豆が使われています。
大阪発の全国区のお店が少ないのがさびしいところなのですが、たとえば丸福珈琲やヒロコーヒーなどが近いといえると思います。
海外のサードウェイブは卸が中心

サードウェイブというとインダストリアルなかっこいい店舗デザインや、スペシャリティ豆をつかった浅煎りなどが特徴に上げられますが、本質は焙煎設備を持つ卸だということです。
卸といっても小売りではなく業務用です。なので焙煎能力は巨大です。
典型的なのは日本でもおなじみになったブルーボトルです。清澄白河の最初の店舗内に巨大な焙煎設備をつくりました。
というよりは焙煎施設に小規模なカフェを併設しているといったほうが正確でしょう。
清澄白河に出店したことをインタビューでもよく聞かれていましたが、本質は焙煎工場なわけですから、むしろ銀座や表参道などにだすほうがおかしいのです。
スターバックスはたとえば今までは日本では焙煎施設を持っていなかったので、アメリカ本土からコンテナを船で一か月かけて運んでいました。
これだとどうしても豆の鮮度は落ちてしまいます。
ただスタバの主力商品はミルクや砂糖をたっぷりといれたカフェラテなので、豆のおいしさをそのまま味わうブラックを楽しむお客さんの割合は相対的に少ないと思われます。
そのため今までのところは鮮度が最重要視されてきたわけではなかったと思われます。
ただ昨今のサードウェイブのトレンドから刺激を受けて、日本でも焙煎を始めるようです。
これに対してドトールなどは日本のブランドということもあって、従来から日本で焙煎した新鮮な豆を供給しています。
この本は開業目的の人へも有用

この本では最後に開業支援についての項目もあります。
堀口さん自身、バブル時代、テナントの保証金が1000万円を超えたぐらいの苦しい時期に個人店を開業されて苦労されたそうですから、その経験をノウハウとして次世代に伝えていきたいという思いがあります。
そのため安易な開業は薦めず、準備に時間をかけることを重要視しています。
特に味を見分けるテイスティングやカッピングの技術と舌の育成は一朝一夕にはできないので、ある程度の修業期間が必要になります。
お寿司屋さんにいくとどうしても握りの技術に目が行きますが、握り自体はある意味誰でもそれなりの時間をかければうまくなります。
お寿司屋さんのレベルを分けるのは仕入れです。
仕入れの目利きの技術とセンス、そして仕入れのルートを開拓するのは一朝一夕にはできないからです。
堀口さんのアドバイスでおもしろいのは、とにかくほかの店と違うところを20点つくってみなさいということです。
20点ちがえば、お客様は店の個性としてその違いを認めてくれるからです。
隣にスターバックスができても問題のないような個性ある店を作りなさいといいます。
これって簡単に言いますが大変なことですよね。でも堀口さんの言われる通り、個性が際立っていれば隣にスタバができても問題ないはずなのです。
堀口さんは脱サラして喫茶店を開いた方です。始めから珈琲店で働いて独立したわけではありません。
このため発想が柔軟で視野が広く、経営と珈琲の探求へのバランスがとれていることが堀口さんを結果的に珈琲業界の新しいトレンドをけん引してきた人物にしたのだと思います。
脱サラしてとりあえず飲食店をやれる体力があるかどうかを他店でバイトして確認するような準備の周到さです。
単に喫茶店をやろうというのではなく、はじめから喫茶、小売り、卸の3本柱でやろうと決めていたそうです。
喫茶だけでは苦しい、生き残りのためのリスクヘッジとしてまだだれもやっていない小売りと卸という要素を付け加えて出発されたのです。
珈琲を選んだのも当時料理人としては年を取りすぎていて第一人者にはなれないという冷静な判断からです。
自分が勝てる可能性のある土俵を選び、用意周到にリスクヘッジをかけながら果敢に新しい道を開拓していくというのは、どの分野であっても応用が利く普遍的な手法だと思います。
ただし誰でもやれることではないですよね。この本は堀口珈琲の作法がコンパクトにつまっているので少し古く(出版は2009年)なっていますがお勧めです。
堀口さんは社長職を引かれてハーフリタイアされて、新しい社長である伊藤亮太氏が書かれた最新の本(2016)が「常識が変わる スペシャルティコーヒー入門」になります。