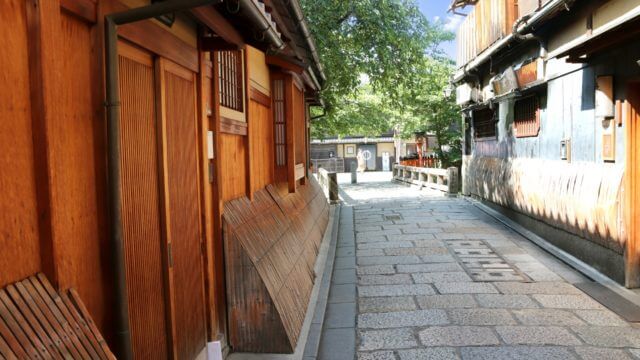Contents
『みるみる高血圧が下がる本』渡辺尚彦監修 笠倉出版

高血圧は今や日本人の国民病ともいうべき症状になっています。
高血圧の診断を受けた方は、食事内容や日ごろの運動習慣を見直すようにお医者さんから言われていることだと思います。
それでは具体的に高血圧を改善してくれる食事法とはどのようなものでしょうか。
ここでは、渡辺尚彦先生が監修された『みるみる高血圧が下がる本』の内容を一部紹介しながら、血圧を下げる食事法、特にDASH食と呼ばれるダイエット法について解説してみたいと思います。
高血圧を予防してくれるDASH食っていったい何?
DASH食とは英語で”Dietary Approaches to Stop Hypertension”の頭文字をとったもので、「高血圧を防いでくれる食事法」という意味です。
DASH食の特徴を簡単に言えば、血圧をあげる食材を外し、血圧を下げる食材の割合をあげるということになります。
下の表は本書にも記載されているもので、日本病態栄養学会のテキストにあるDASH食の栄養成分の割合と分量を表したものです。
| 栄養組成 | 日本の食事 | DASH食 |
| 脂肪(%) | 23.7 | 27 |
| 飽和脂肪酸(%) | 6.1 | 6 |
| たんぱく質(%) | 15.8 | 18 |
| 繊維質(%) | 15.5 | 31 |
| コレステロール | 446 | 150 |
| ナトリウム | 4.8 | 3 |
| カリウム | 1.9 | 4.7 |
| カルシウム | 605 | 1240 |
| マグネシウム | 288 | 500 |
日本の食事というのは日本人の平均的な食事における各成分の摂取量と割合を表しています。
パッと見て気が付くのは繊維質の割合がDASH食では倍になっていること、コレステロールの値が3分の1になっていること、ミネラルではナトリウム以外は大幅に増えていることなどです。
食材でいうと血圧を下げてくれるのは、野菜、果物、魚介類、低脂肪の乳酸品、大豆食品、海藻類です。
逆に上げてしまう食材は、肉、ソーセージなどの加工食品、ハム、バター、生クリームなどです。
栄養素でいえば、カリウム、マグネシウム、たんぱく質、食物繊維を増やし、コレステロールと飽和脂肪酸は減らします。
野菜や果物のなかでは色の濃いものを目安にすれば選びやすいと思います。
かぼちゃ、りんご、メロン、バナナ、小松菜、モロヘイヤ、ほうれんそうなどです。
魚介類では青魚が中心になります。アジ、イワシ、タコ、イカなどです。
乳酸品については低脂肪の牛乳やヨーグルトなどです。
僕は血圧が高くなると、納豆や豆腐の割合を増やして、ごはんなどの糖質類を減らします。納豆など大豆食品には血圧を下げる成分が含まれています。
食パンはほとんど食べなくなったので、バターなどは食べません。
血圧をあげてしまう要因の一つに塩分の摂りすぎがあります。しかし食材には塩分を体外に排泄してくれるものもあります。それがカリウムが豊富に含まれるほうれんそうやいも類です。
カリウムが含まれる食材は、ほんれんそう、さといも、さつまいも、春菊、トマト、ジャガイモ、キウイ、アボガド、バナナなどです。
カリウムは過剰摂取しても尿から排出されますので問題ありませんが、
DASH食は基本的にはカロリーが高いものを減らして、カロリーの低い食材を増やすというシンプルなものですから、誰でもそれなりに意識すれば選択に困ることはないと思います。
乳製品に含まれるカルシウムが血圧を下げる仕組み

カルシウムが血圧を下げてくれると聞くと初耳の方も多いのではないでしょうか。
DASH食の研究がすすむにつれて、カルシウムをカリウム、マグネシウム、食物繊維と一緒にとることで、血圧を下げる効果が増幅されることがわかってきたのです。
カルシウムというと牛乳を思い浮かべますが、納豆や豆腐、厚揚げなどの大豆食品も牛乳に負けず劣らずにカルシウムが入っています。
またカルシウムは葉物野菜にも入っています。小松菜や菜の花、モロヘイヤや大根にはカロテノイドや葉酸も含まれていますので、カルシウムと一緒に摂取できます。
カロテノイドというのはビタミンAと考えてもらって結構です。カロテノイドというのはビタミンAが不足したときにビタミンに切り替わる成分で、例えばニンジンのあのオレンジ色の色素がカロテノイドです。
ただし、カルシウムは筋肉や血管の細胞に入り込んで血管の収縮を助ける機能を持っているます。血管が収縮すると血流が強くなり血圧はあがります。
しかしマグネシウムはカルシウムの血管収縮機能をコントロールする働きがあります。またマグネシウムは交感神経の働きを鎮静化して血管を拡張させる機能もあります。
このためマグネシウムはカルシウムが過度に血管を収縮させないようにうまく調整してくれるのです。
このマグネシウムとカルシウムの摂取量の比率は1:2が最適な割合だといわれています。
マグネシウムが多く含まれている食材は、海藻類、ナッツ類、大豆食品、玄米・雑穀などです。
ナッツ類で注意することは、市販の塩分過多の商品は控えることです。塩分がついていると血圧をあげますし、ナッツ類はカロリーも高いので食べ過ぎにつながります。
お薦めはコンビニでも売られている塩分抜きのナッツ商品です。塩と油抜きのミックスナッツとか素焼きナッツという商品名で売られていますね。
食習慣の見直しによる減量で血圧をコントロール
血圧を下げてくれる方法は、食生活の内容とともにその量にあります。
適切なカロリーコントロールで減量を実現すれば、血圧を大幅に下げる効果があります。
こちらのデイケアのブログ記事(禁煙と減量でどれくらい血圧は下がる?)によりますと、
今までの治療データから体重が1キロ減でどれだけ血圧が下がるのかがおおよそわかっています。体重では1キロ減るごとに平均して4ml程度下がります。
もう少し正確に言うと、血圧は最初の5キロの減量までは下がり始めません。しかしそこを超えて減量すると1キロあたり4ml下がるということになります。つまり10キロ痩せると20ml下がることになります。
こちらのブログでも書かれていますが、血圧は年齢とともに増加しますが、その一つの要因が加齢とともに体重が増えることです。
なので体重を減らしてやることで、血圧も若い時の状態に戻すことができるのです。
個人的な経験でいえば、自分は糖質制限をしたとき血圧が大幅に下がりました。ダイエットコラム記事(二度とリバウンドしない習慣化ダイエットで人生を変える)でも血圧の推移を書いていますが、最高血圧が139から127、最低血圧が85から80に減りました。
この効果についてはやはり食生活の内容を変えたことと糖質制限による減量によるものだと思います。
期間としては2か月程度なので、食生活の変化がどれだけ血圧低下につながるか理解できると思います。
運動習慣で薬しらずの血圧コントロール

血圧を下げてくれる習慣としてもう一つ大事なのは運動習慣です。
運動習慣といっても血圧低下に向いているのは無酸素運動ではなく有酸素運動です。
筋トレのような無酸素運動は血圧を一気に上げてしまうのでお勧めできません。血圧が高い状態で筋トレをすると気分が悪くなったり、吐き気がしたりしてよろしくありません。
降圧に効果的なのはジョギングやウオーキングなどの有酸素運動です。
高血圧によるだるさや疲労感を感じている人でも、軽いジョギングやサイクリングをすると気分がすっきりすることがあります。
これは運動後に血圧が下がっているからでしょう。
ただし無酸素有酸素の区別に関わらず、運動は一般的には血圧をあげる行為ですので、有酸素運動であっても自分の体調と相談してどのくらいなら問題なく続けていけるのか、また運動前運動後の血圧の変化はどの程度なのかを自分で把握されることをおすすめします。
有酸素運動といっても心拍数を大きく上げるような激しい運動は必要ありません。無理のない低強度の運動でも血圧を下げるには十分なことが医学的に証明されているのです。
無理のない低強度の運動とは、息が上がらない程度で30分程度のウオーキングなどです。
注意点はしっかりと運動前後に水分をとることです。喉が渇く前に水分をとりましょう。
この他体の柔軟性をつけることで血管の柔軟性もついてきますのでストレッチなども血圧の低下に有効です。